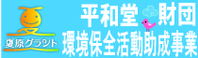2015年06月25日
あなたは果たして「カスミサンショウウオ」を発見できるか!!
SAVE JAPAN プロジェクト イベント参加者募集中です。
滋賀県の湖北で、かわいい幼生を見られる!?
※このイベントは台風の影響のために中止されました。
改めて観察会等を行います。詳細が決まり次第このブログでもお知らせいたしますので、
少々お待ちください。
田村山生き物ネットワーク主催
「あなたは果たして「カスミサンショウウオ」を発見できるか!!」
2015年07月18日(土)開催します。
参加者募集中です。
詳しくはSAVE JAPAN プロジェクトサイトにアクセスしてください↓
http://savejapan-pj.net/sj2015/shiga/event/post.html
かわいいカスミサンショウウオの写真が見られます!

滋賀県の湖北で、かわいい幼生を見られる!?
※このイベントは台風の影響のために中止されました。
改めて観察会等を行います。詳細が決まり次第このブログでもお知らせいたしますので、
少々お待ちください。
田村山生き物ネットワーク主催
「あなたは果たして「カスミサンショウウオ」を発見できるか!!」
2015年07月18日(土)開催します。
参加者募集中です。
詳しくはSAVE JAPAN プロジェクトサイトにアクセスしてください↓
http://savejapan-pj.net/sj2015/shiga/event/post.html
かわいいカスミサンショウウオの写真が見られます!

Posted by しがNPOセンター at
11:10
│SAVEJAPANプロジェクト
2015年06月03日
住民投票の課題と可能性
しがNPOセンター 代表理事
阿部圭宏
大阪市を廃止し、特別区を設置するかどうかの是非を問う住民投票が終わった。今回の住民投票は、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づくもので、これまでにない大規模の住民投票となったこと、投票結果に拘束力を持つという点でも注目をされた。投票運動が通常の選挙と違い、まさに主張の違いを出して行われることもその特徴と言えるかもしれない。
大阪市の住民投票の約1か月前に滋賀県高島市でも住民投票が行われた。市役所の庁舎整備に関するもので、合併時に定めた位置で新庁舎を整備するか、現庁舎での改築増築かを問うものであった。現庁舎での改築増築をめざす市長が庁舎の位置を定める条例の改正を求めるも、議会で2回にわたり否決(地方自治法の規定で出席議員の3分の2以上の同意が必要)され、市長提案で住民投票となった。告示から投票までにあまり時間がなく、しかも投票日が県議選と同日となったことで、投票運動に制限がかかった。投票率67.85%で、投票結果は現庁舎での改築増築賛成が65%を超えた。住民投票の結果は、大阪市と違い、市長や議会は結果を尊重しなければならないというものだったが、住民投票結果を受けた臨時議会ではまたしても否決された。
住民投票は、住民の意思に基づき地方自治が行われる住民自治にとってとても大切な仕組みだ。通常、地方自治は、ともに選挙で選ばれた首長と議員がそれぞれの機能を果たすという二元代表制をとっているため、住民自らが政策に対しての意思を行動として表すことが難しい状況にある。こうした地方自治の現状を踏まえまがら、住民の意思を政策に反映し、住民自治を広げるために行われているのが住民投票だ。新潟県巻町での原発建設の是非を問う住民投票、徳島県吉野川可動堰化の是非を問う住民投票などで注目された住民投票が、より一般的な形で行われるように、常設型のものとして制度化される事例も出てきている。
しかし、こうした住民投票の現場を見ると、実は課題が多いことに気づかされる。大阪市の場合は、投票率に関わらず住民投票の結果が政策決定に直結するもので拘束型と呼ばれ、ある意味分かりやすい構図となっていた。こうした仕組みは、首長や議員の解職、地方議会の解散の直接請求によって行われる住民投票と同じである。一方、高島市のような住民投票は、諮問型と呼ばれ、結果には拘束されないが、首長も議会も結果を尊重することが求められている。その意味では、住民投票結果に従わない議会というものの存在意義の正当性が問われていると言えるだろう。高島市の事例でもう一つ問題だと思われるのは、そもそも市長に発議権を与えるのはどうかということである。常設型の住民投票条例を持っている場合は、首長や議会に発議権を与えることが多いが、発議権に何らかの制約を付けている。今回は、経済団体からの住民投票の発議の要望を根拠に条例提案されているので、これもまた正当性に疑問がわく。さらに、投票日を県議選と同日にしたことでの投票運動の制限も問題がある(だからと言って、住民投票が無効ということにはならないのは当然であるが)。あるいは、小平市や伊賀市で行われた住民投票では、投票率が投票者の総数が投票資格者の2分の1に満たない場合は不成立として開票されなかった。これにも問題が多い。
このように住民投票はまだまだ多くの問題を抱えている。住民投票はポピュリズムを生み出すとか、住民投票は間接民主制(代表民主制)を否定するものだとか、さらには、住民にそもそもまともな判断ができるのかというとんでもないものも含め、否定的な意見が多いのも事実だ。では、議会は果たして万全に機能しているのかというと、多くの方は否定的な意見を言うだろう。今の地方自治制度の中で住民自治を進展させていくには、住民投票の仕組みは欠かせない。重要案件の決定は住民投票でということが当たり前になれば、必ず民主主義は発展する。その意味においても、住民投票への理解が進み、各地に常設型の住民投票条例が制定されることを期待したい。
阿部圭宏
大阪市を廃止し、特別区を設置するかどうかの是非を問う住民投票が終わった。今回の住民投票は、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づくもので、これまでにない大規模の住民投票となったこと、投票結果に拘束力を持つという点でも注目をされた。投票運動が通常の選挙と違い、まさに主張の違いを出して行われることもその特徴と言えるかもしれない。
大阪市の住民投票の約1か月前に滋賀県高島市でも住民投票が行われた。市役所の庁舎整備に関するもので、合併時に定めた位置で新庁舎を整備するか、現庁舎での改築増築かを問うものであった。現庁舎での改築増築をめざす市長が庁舎の位置を定める条例の改正を求めるも、議会で2回にわたり否決(地方自治法の規定で出席議員の3分の2以上の同意が必要)され、市長提案で住民投票となった。告示から投票までにあまり時間がなく、しかも投票日が県議選と同日となったことで、投票運動に制限がかかった。投票率67.85%で、投票結果は現庁舎での改築増築賛成が65%を超えた。住民投票の結果は、大阪市と違い、市長や議会は結果を尊重しなければならないというものだったが、住民投票結果を受けた臨時議会ではまたしても否決された。
住民投票は、住民の意思に基づき地方自治が行われる住民自治にとってとても大切な仕組みだ。通常、地方自治は、ともに選挙で選ばれた首長と議員がそれぞれの機能を果たすという二元代表制をとっているため、住民自らが政策に対しての意思を行動として表すことが難しい状況にある。こうした地方自治の現状を踏まえまがら、住民の意思を政策に反映し、住民自治を広げるために行われているのが住民投票だ。新潟県巻町での原発建設の是非を問う住民投票、徳島県吉野川可動堰化の是非を問う住民投票などで注目された住民投票が、より一般的な形で行われるように、常設型のものとして制度化される事例も出てきている。
しかし、こうした住民投票の現場を見ると、実は課題が多いことに気づかされる。大阪市の場合は、投票率に関わらず住民投票の結果が政策決定に直結するもので拘束型と呼ばれ、ある意味分かりやすい構図となっていた。こうした仕組みは、首長や議員の解職、地方議会の解散の直接請求によって行われる住民投票と同じである。一方、高島市のような住民投票は、諮問型と呼ばれ、結果には拘束されないが、首長も議会も結果を尊重することが求められている。その意味では、住民投票結果に従わない議会というものの存在意義の正当性が問われていると言えるだろう。高島市の事例でもう一つ問題だと思われるのは、そもそも市長に発議権を与えるのはどうかということである。常設型の住民投票条例を持っている場合は、首長や議会に発議権を与えることが多いが、発議権に何らかの制約を付けている。今回は、経済団体からの住民投票の発議の要望を根拠に条例提案されているので、これもまた正当性に疑問がわく。さらに、投票日を県議選と同日にしたことでの投票運動の制限も問題がある(だからと言って、住民投票が無効ということにはならないのは当然であるが)。あるいは、小平市や伊賀市で行われた住民投票では、投票率が投票者の総数が投票資格者の2分の1に満たない場合は不成立として開票されなかった。これにも問題が多い。
このように住民投票はまだまだ多くの問題を抱えている。住民投票はポピュリズムを生み出すとか、住民投票は間接民主制(代表民主制)を否定するものだとか、さらには、住民にそもそもまともな判断ができるのかというとんでもないものも含め、否定的な意見が多いのも事実だ。では、議会は果たして万全に機能しているのかというと、多くの方は否定的な意見を言うだろう。今の地方自治制度の中で住民自治を進展させていくには、住民投票の仕組みは欠かせない。重要案件の決定は住民投票でということが当たり前になれば、必ず民主主義は発展する。その意味においても、住民投票への理解が進み、各地に常設型の住民投票条例が制定されることを期待したい。
Posted by しがNPOセンター at
12:48
│シリーズ【阿部コラム】
2015年06月01日
2014年度 事業報告と決算書類
2015年5月23日、認定特定非営利活動法人 しがNPOセンターの総会を開催し、
2014年度の事業報告ならびに決算報告を行いました。
2014年4月1日~2015年3月31日
~1年を振り返って~
しがNPOセンターは、認定特定非営利活動法人として昨年度9月に認定され、今後の寄付戦略が大きな課題となっています。また活動や資金源が委託事業によるものの割合が多く、団体として本来の目的を達成するための事業が少ないことも課題のひとつです。このふたつの課題に着目して、今年度から具体的に取り組んだのが「NPO若人エンパワープロジェクト」でした。5本柱のひとつ「市民活動・NPO支援」に関する活動として、これからのNPOを担う若手リーダー育成を目的とし、その財源を寄付で賄うこととしました。寄付をお願いするにあたり若手NPOスタッフが力をつけることの意義について丁寧に説明しながら、それによってもたらされる滋賀県の姿を提示してきました。寄付については、チラシの配布やプレスリリース、また出会った際の声掛けなどを中心に行いましたが、まだまだ周知されておらず、寄付金も目標額に達していないのが現状です。2年間に亘るプロジェクトでもあるため、今後は集中的な広報を再び行うこと、積極的な声掛け、また新たな寄付先の開拓が重要だと思っています。
NPO法が改正され、滋賀県内の認定・仮認定NPO法人が急激に増加し、2015年3月には13団体となりました。認定取得の動議付けとしては、控除が可能となり寄付が集まりやすいのではないかということが大きいと思われます。しかし認定取得によって寄付が集まるのではなく、いつ誰からどのようにどのくらい集めるのかといったことも含めた寄付戦略が重要で、そこでの悩みが大きいとの話も聞きました。また事務的なことについての疑問を抱えているケースもあります。そこで滋賀県内で認定・仮認定を取得したNPO法人が情報交換をする場「認定・仮認定NPO法人情報交換会」を開催しました。1団体欠席ではあったが12団体、滋賀県と淡海ネットワークセンターからのオブザーバー参加があり、関心の高さが伺えました。意見交換では様々な課題が上がりましたが、団体ごとに工夫やアイデアが紹介され、他団体への刺激や参考となることが多かったようです。こういった場の設定は他の団体には難しく、しがNPOセンターならではの取り組みであったと思います。
東日本大震災を機に活動の柱として「災害ボランティアコーディネート事業」を掲げ、被災地の支援や被災者支援、滋賀県内での災害ボランティアネットワーク構築に取り組んでいます。しかし、どの取り組みについても資金獲得・確保が困難になってきている。被災地・被災者支援については資金の問題もさることながら、刻々と変化していく状況によって取り組みの視点や適性などを検証し、柔軟な対応を心掛けていくことが重要です。従来からのやり方で淡々と進めていくのは効果がないだけではなく、支障をきたす場合もあることを肝に銘じる必要があります。こうしたことからも、連合愛のカンパの助成で実施する「災害ボランティアコーディネーター養成講座」は、本来の目的を達成するために自ら資金獲得のために動いた事業として、その果たす役割は大きいものがあります。現在来年度講座実施に向けての準備中ですが、講座申込状況からニーズと意欲が高いことが伺われます。
環境助成金事業「夏原グラント」の運営事務局を担い3年が経過しました。助成金を受けている団体数も増え活動が広がってきているとはいえ、一般への認知度はまだ低く感じています。今後、京都への展開を足掛かりに淀川水系にかかる範囲へこの制度を広めていきたいという平和堂財団の意向を踏まえ、より広範囲で多様な層への広報、周知が必要だと感じています。そのためには多様な広報ツールを使うことが重要ですし、3年経過した中で、今後の応募団体数の減少傾向、助成3年経過後の団体サポート、環境保全活動のあり方についての周知など、課題にしっかりと取り組んでいこうと考えています。
↓2014年度事業報告書
 (PDF: 450.67KB)
(PDF: 450.67KB)
↓2014年度決算書類
 (PDF: 226.59KB)
(PDF: 226.59KB)
2014年度の事業報告ならびに決算報告を行いました。
2014年4月1日~2015年3月31日
~1年を振り返って~
しがNPOセンターは、認定特定非営利活動法人として昨年度9月に認定され、今後の寄付戦略が大きな課題となっています。また活動や資金源が委託事業によるものの割合が多く、団体として本来の目的を達成するための事業が少ないことも課題のひとつです。このふたつの課題に着目して、今年度から具体的に取り組んだのが「NPO若人エンパワープロジェクト」でした。5本柱のひとつ「市民活動・NPO支援」に関する活動として、これからのNPOを担う若手リーダー育成を目的とし、その財源を寄付で賄うこととしました。寄付をお願いするにあたり若手NPOスタッフが力をつけることの意義について丁寧に説明しながら、それによってもたらされる滋賀県の姿を提示してきました。寄付については、チラシの配布やプレスリリース、また出会った際の声掛けなどを中心に行いましたが、まだまだ周知されておらず、寄付金も目標額に達していないのが現状です。2年間に亘るプロジェクトでもあるため、今後は集中的な広報を再び行うこと、積極的な声掛け、また新たな寄付先の開拓が重要だと思っています。
NPO法が改正され、滋賀県内の認定・仮認定NPO法人が急激に増加し、2015年3月には13団体となりました。認定取得の動議付けとしては、控除が可能となり寄付が集まりやすいのではないかということが大きいと思われます。しかし認定取得によって寄付が集まるのではなく、いつ誰からどのようにどのくらい集めるのかといったことも含めた寄付戦略が重要で、そこでの悩みが大きいとの話も聞きました。また事務的なことについての疑問を抱えているケースもあります。そこで滋賀県内で認定・仮認定を取得したNPO法人が情報交換をする場「認定・仮認定NPO法人情報交換会」を開催しました。1団体欠席ではあったが12団体、滋賀県と淡海ネットワークセンターからのオブザーバー参加があり、関心の高さが伺えました。意見交換では様々な課題が上がりましたが、団体ごとに工夫やアイデアが紹介され、他団体への刺激や参考となることが多かったようです。こういった場の設定は他の団体には難しく、しがNPOセンターならではの取り組みであったと思います。
東日本大震災を機に活動の柱として「災害ボランティアコーディネート事業」を掲げ、被災地の支援や被災者支援、滋賀県内での災害ボランティアネットワーク構築に取り組んでいます。しかし、どの取り組みについても資金獲得・確保が困難になってきている。被災地・被災者支援については資金の問題もさることながら、刻々と変化していく状況によって取り組みの視点や適性などを検証し、柔軟な対応を心掛けていくことが重要です。従来からのやり方で淡々と進めていくのは効果がないだけではなく、支障をきたす場合もあることを肝に銘じる必要があります。こうしたことからも、連合愛のカンパの助成で実施する「災害ボランティアコーディネーター養成講座」は、本来の目的を達成するために自ら資金獲得のために動いた事業として、その果たす役割は大きいものがあります。現在来年度講座実施に向けての準備中ですが、講座申込状況からニーズと意欲が高いことが伺われます。
環境助成金事業「夏原グラント」の運営事務局を担い3年が経過しました。助成金を受けている団体数も増え活動が広がってきているとはいえ、一般への認知度はまだ低く感じています。今後、京都への展開を足掛かりに淀川水系にかかる範囲へこの制度を広めていきたいという平和堂財団の意向を踏まえ、より広範囲で多様な層への広報、周知が必要だと感じています。そのためには多様な広報ツールを使うことが重要ですし、3年経過した中で、今後の応募団体数の減少傾向、助成3年経過後の団体サポート、環境保全活動のあり方についての周知など、課題にしっかりと取り組んでいこうと考えています。
↓2014年度事業報告書
↓2014年度決算書類