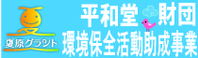2019年05月27日
2018年度 事業報告と決算書類
2019年5月17日、認定特定非営利活動法人 しがNPOセンターの総会を開催し、
2018年度の事業報告ならびに決算報告を行いました。その報告の詳しい内容は報告書をダウンロードしてご覧ください。
2018年度は、しがNPOセンター設立から10年を迎える節目の年となりました。法人化してからも8期を数え、2013年度に取得した認定NPO法人も更新時期を迎え、無事認定更新することができました。
認定取得にあたって、寄附金の重点充当プログラムとしてきた人材育成と災害支援にも積極的に取り組みました。2期4年にわたってセンターが実施してきた「NPO若人エンパワープロジェクト」は、年齢枠を取り払うなど新しいかたちの「NPO人育ちプロジェクト」として再始動することとなり、8団体から10名のメンバーが参加しました。
災害支援では、台風が3回も上陸しましたが、滋賀での被害は少なかったものの西日本豪雨水害をもたらし大きな被害が出ました。センターとしては、三原市の子ども支援を中心に活動するとともに、東日本大震災の被災地復興状況の視察などを行いました。また3年間取り組んできた災害ボランティアコーディネーター養成のフォローアップ事業を実施しました。とは言え、センターやセンターが取り組んでいる活動への共感を高め、寄附金を集めていくことに関してはまだ十分とは言えず、結果として寄附金を広く募っていくことには、まだ課題が多いと言わざるを得ない状況でした。
市民活動支援のベーシックな活動としての相談事業は、センターにとっても重要な位置付けとなっています。これまでは、有料相談のみを報告書に記載していたことからニーズが多くない印象を与えてきましたが、「草津市協働コーディネーター業務」、「夏原グラント」、2018年度から新たに始まった「できるコトづくり制度」などの協働委託業務を通じて、多様な相談に応じてきている実態がありました。今年度導入したセールフォース(名簿管理ソフト)に記録を載せることで、これまで以上に団体の課題や弱みが分かるようになっており、今後の支援につなげていくためのヒントが得られました。
草津市の協働コーディネート業務は、現在の草津市立まちづくりセンターが(仮)総合交流センターへの移行時期が決まったことで、機能の整理や管理方法の検討など、コミュニティ事業団の今後も含め、その対応が求められることとなりました。
一方、企業団体との協働関係は新しい展開となっています。平和堂財団の環境保全助成金事業「夏原グラント」に加え、生活協同組合コープしがとの「できるコトづくり制度」がスタートし、大和リースが展開する「まちづくりスポット」の開設準備を行うこととなりました。
「夏原グラント」は、2012年度から助成が始まり、2018年度までで助成を受けたのは延べ314団体、助成金総額は90,951,000円となっていて、滋賀県および京都府の自然環境保全とその活動を支える団体に対して大きく貢献しています。民間の助成金規模としては滋賀県では突出したものであり、このことを広く伝えていく必要があります。また市民活動支援の強みを活かして、助成を受けている団体の継続・発展のために講座や相談会、個別コンサルティングにも対応してきたことで、財団から助成を受けている団体との関係性の構築、団体や活動の情報収集、活動中の問題解決や組織運営のサポートなどを評価していただいています。2018年度までで助成団体新しい枠組みなどを構築することでステージが増え、多くの団体とのつながりができてきています。それぞれの団体と、丁寧な関係を築くことを大切にしていきたいものです。全体スケジュールや事務作業手順などは、今まで関わってきたスタッフの暗黙知で動いている状況で、これを可視化しておく必要があります。
「できるコトづくり制度」はコープしがが主宰し、さまざまな「想い」や「願い」を持った個人や団体が新たな一歩を踏み出すための学習の場の提供と、それらを実現させるために必要な資金の助成とでなっていて、しがNPOセンターがプログラム作成等を行うとともに運営事務局を担っていいます。2018年度は、助成金の募集、決定を行い、次年度につなげることとしています。これらの企画運営には、夏原グラント事務局でのノウハウが活かされスムーズな運営ができました。
「まちづくりスポット」は、大和リースが全国で展開している地域交流拠点で、地域課題の解決につながる活動を支援することや多様なセクターのつながりをつくるなど、当センターの活動趣旨にも合致することから、まちづくりスポットの運営を担うこととし、開設に向けた準備を進めてきました。開設は2019年秋が予定されていて、本格的な準備作業に入ります。
災害ボランティアコーディネート事業の中では、前述の活動のほか、近畿ろうきんのNPOパートナーシップ制度を使って、しがNPOセンターが事務局を担っている「災害支援市民ネットワークしが」での研究会を開催しました。
↓2018年度事業報告書
 (PDF: 790.39KB)
(PDF: 790.39KB)
↓2018年度決算書類
 (PDF: 1018.67KB)
(PDF: 1018.67KB)
2018年度の事業報告ならびに決算報告を行いました。その報告の詳しい内容は報告書をダウンロードしてご覧ください。
2018年度 事業報告書
2018年4月1日~2019年3月31日
概 要
2018年4月1日~2019年3月31日
概 要
2018年度は、しがNPOセンター設立から10年を迎える節目の年となりました。法人化してからも8期を数え、2013年度に取得した認定NPO法人も更新時期を迎え、無事認定更新することができました。
認定取得にあたって、寄附金の重点充当プログラムとしてきた人材育成と災害支援にも積極的に取り組みました。2期4年にわたってセンターが実施してきた「NPO若人エンパワープロジェクト」は、年齢枠を取り払うなど新しいかたちの「NPO人育ちプロジェクト」として再始動することとなり、8団体から10名のメンバーが参加しました。
災害支援では、台風が3回も上陸しましたが、滋賀での被害は少なかったものの西日本豪雨水害をもたらし大きな被害が出ました。センターとしては、三原市の子ども支援を中心に活動するとともに、東日本大震災の被災地復興状況の視察などを行いました。また3年間取り組んできた災害ボランティアコーディネーター養成のフォローアップ事業を実施しました。とは言え、センターやセンターが取り組んでいる活動への共感を高め、寄附金を集めていくことに関してはまだ十分とは言えず、結果として寄附金を広く募っていくことには、まだ課題が多いと言わざるを得ない状況でした。
市民活動支援のベーシックな活動としての相談事業は、センターにとっても重要な位置付けとなっています。これまでは、有料相談のみを報告書に記載していたことからニーズが多くない印象を与えてきましたが、「草津市協働コーディネーター業務」、「夏原グラント」、2018年度から新たに始まった「できるコトづくり制度」などの協働委託業務を通じて、多様な相談に応じてきている実態がありました。今年度導入したセールフォース(名簿管理ソフト)に記録を載せることで、これまで以上に団体の課題や弱みが分かるようになっており、今後の支援につなげていくためのヒントが得られました。
草津市の協働コーディネート業務は、現在の草津市立まちづくりセンターが(仮)総合交流センターへの移行時期が決まったことで、機能の整理や管理方法の検討など、コミュニティ事業団の今後も含め、その対応が求められることとなりました。
一方、企業団体との協働関係は新しい展開となっています。平和堂財団の環境保全助成金事業「夏原グラント」に加え、生活協同組合コープしがとの「できるコトづくり制度」がスタートし、大和リースが展開する「まちづくりスポット」の開設準備を行うこととなりました。
「夏原グラント」は、2012年度から助成が始まり、2018年度までで助成を受けたのは延べ314団体、助成金総額は90,951,000円となっていて、滋賀県および京都府の自然環境保全とその活動を支える団体に対して大きく貢献しています。民間の助成金規模としては滋賀県では突出したものであり、このことを広く伝えていく必要があります。また市民活動支援の強みを活かして、助成を受けている団体の継続・発展のために講座や相談会、個別コンサルティングにも対応してきたことで、財団から助成を受けている団体との関係性の構築、団体や活動の情報収集、活動中の問題解決や組織運営のサポートなどを評価していただいています。2018年度までで助成団体新しい枠組みなどを構築することでステージが増え、多くの団体とのつながりができてきています。それぞれの団体と、丁寧な関係を築くことを大切にしていきたいものです。全体スケジュールや事務作業手順などは、今まで関わってきたスタッフの暗黙知で動いている状況で、これを可視化しておく必要があります。
「できるコトづくり制度」はコープしがが主宰し、さまざまな「想い」や「願い」を持った個人や団体が新たな一歩を踏み出すための学習の場の提供と、それらを実現させるために必要な資金の助成とでなっていて、しがNPOセンターがプログラム作成等を行うとともに運営事務局を担っていいます。2018年度は、助成金の募集、決定を行い、次年度につなげることとしています。これらの企画運営には、夏原グラント事務局でのノウハウが活かされスムーズな運営ができました。
「まちづくりスポット」は、大和リースが全国で展開している地域交流拠点で、地域課題の解決につながる活動を支援することや多様なセクターのつながりをつくるなど、当センターの活動趣旨にも合致することから、まちづくりスポットの運営を担うこととし、開設に向けた準備を進めてきました。開設は2019年秋が予定されていて、本格的な準備作業に入ります。
災害ボランティアコーディネート事業の中では、前述の活動のほか、近畿ろうきんのNPOパートナーシップ制度を使って、しがNPOセンターが事務局を担っている「災害支援市民ネットワークしが」での研究会を開催しました。
↓2018年度事業報告書
↓2018年度決算書類
2019年05月21日
「新書de読書会」 第31回のお知らせ
「新書de読書会」 第31回の課題本は「データの罠~世論はこうして作られる」です。
「本書は、さまざまなデータを検証することで、データの罠を見抜き、それらに振り回されない“正しい”情報の読みとり方ーデータリテラシーを提案する。」新潮社新書サイトより引用
ご参加をお待ちしています。
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
■開催日時:2019年6月17日(月)
■課題本:「データの罠~世論はこうして作られる」田村 秀(集英社新書)
■開催時間:19:00 ~ 21:00
■会場:草津市立まちづくりセンター304
■参加のルール
①課題本をご持参ください。読み切っていなくても結構です。
②積極的に発言しましょう。
③意見への反論はOK、でも否定や誹謗中傷などはNG。
④読書会中の画像をネット上への公開する場合、参加者へ了解をとりましょう。
■進め方
しがNPOセンターの代表理事・阿部圭宏が進行します。阿部以外の参加者が課題本を選定したときには、その方が進行します。
本全体の感想やキーワードを深めての議論を予定します。
話の展開によっては、本から離れた話題にも花が咲くこともあります。
■参加費
500円
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
■参加申込み
参加を希望される方は準備の都合等がありますので、下記をメールにてお知らせください。
申し込みがなくても、当日飛び入り参加OKです。
1・参加者名、所属
2・連絡先(当日連絡がとれる携帯電話番号などをお教えください)
■お問い合わせ・申込先
認定特定非営利活動法人しがNPOセンター
TEL:0748-34-3033 FAX:020-4664-3933
E-mail:shiga.npo@gmail.com
■今後の予定
第32回7月22日 「日本が売られる」堤未果(幻冬舎新書)※都合により課題本を変更しました
第33回8月19日 「移民クライシス」出井康博(角川新書)※都合により課題本を変更しました
第34回9月 9日 「地方議会を再生する」相川俊英(集英社新書)
「本書は、さまざまなデータを検証することで、データの罠を見抜き、それらに振り回されない“正しい”情報の読みとり方ーデータリテラシーを提案する。」新潮社新書サイトより引用
ご参加をお待ちしています。
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
■開催日時:2019年6月17日(月)
■課題本:「データの罠~世論はこうして作られる」田村 秀(集英社新書)
■開催時間:19:00 ~ 21:00
■会場:草津市立まちづくりセンター304
■参加のルール
①課題本をご持参ください。読み切っていなくても結構です。
②積極的に発言しましょう。
③意見への反論はOK、でも否定や誹謗中傷などはNG。
④読書会中の画像をネット上への公開する場合、参加者へ了解をとりましょう。
■進め方
しがNPOセンターの代表理事・阿部圭宏が進行します。阿部以外の参加者が課題本を選定したときには、その方が進行します。
本全体の感想やキーワードを深めての議論を予定します。
話の展開によっては、本から離れた話題にも花が咲くこともあります。
■参加費
500円
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
■参加申込み
参加を希望される方は準備の都合等がありますので、下記をメールにてお知らせください。
申し込みがなくても、当日飛び入り参加OKです。
1・参加者名、所属
2・連絡先(当日連絡がとれる携帯電話番号などをお教えください)
■お問い合わせ・申込先
認定特定非営利活動法人しがNPOセンター
TEL:0748-34-3033 FAX:020-4664-3933
E-mail:shiga.npo@gmail.com
■今後の予定
第32回7月22日 「日本が売られる」堤未果(幻冬舎新書)※都合により課題本を変更しました
第33回8月19日 「移民クライシス」出井康博(角川新書)※都合により課題本を変更しました
第34回9月 9日 「地方議会を再生する」相川俊英(集英社新書)
2019年05月01日
大津市の支所統廃合とまちづくりの課題
しがNPOセンター
代表理事 阿部 圭宏
大津市はこれまで合併により市域を広げ、その結果として北部・中部・南部の微妙なバランスの上で市政運営が行われてきた。ハコモノも北部・中部・南部の3カ所に配置をすることで、市民の不満を抑えてきた面がある。同じように、地域の微妙なバランスという点では、学区(小学校区)も同様であり、学区単位に支所(市民センター)を置き、自治会が学区自治連合会や市自治連合会というピラミッド構造の中で運営されている面もある。2003年当時(志賀町と合併する前)の市のホームページでは、「大津市のまちづくりは、自治会組織を中心として活動の推進が図られ、大津市自治連合会は48年の歴史をもっています。 現在、市内には627の単位自治会を基本に31学区自治連合会、市自治連合会連携のもとに地域住民の連帯感が培われ、会員相互の親睦活動、地域活動が活発に展開されています」と紹介され、大津市が自治会に力点を置いてきたことが伺える。
2006年には大津市市民活動センターが開設され、行政が市民活動・NPOとの関係性を少し構築する場面も見られるようになったが、基本的には、自治会、自治連合会中心に据えた市政運営がなされてきたことは疑い得ない事実である。
2000年の地方分権一括法の施行を機に、全国で合併の嵐が吹くようになる。合併による市域の拡大に対して、住民に身近な自治の仕組みをつくる動きも活発になっていく。滋賀においても、合併した湖南市、東近江市、長浜市、甲賀市では、地域自治組織として、まちづくり協議会、地域づくり協議会、自治振興会という名称で動き出すが、大津市では全くこうした気運が醸成されてこなかった。自治会加入率は、2007年に70%を割り込み、2018年4月には、60.2%にまで落ち込んでいる。自治会中心主義を掲げられなくなり、次の手段を探る必要があった。そこで、遅ればせながら出てきたのが、支所機能の見直しと地域自治の仕組みとしてのまちづくり協議会である。
自治会加入率の減少は、その連合体である自治連合会を含めた統治機構の正統性に関わる問題である。少なくとも、自治連合会はこれまでのような地域を代表する組織とは強弁できなくなっている。それを補完するものとして、大津市が提案しているのがまちづくり協議会である。なぜ必要なのか、どのようにつくるべきか、運営はどうするのかなど、実際にはなかなか大変であり、行政がていねいに地域への説明を行い、地域の自発性、やる気を起こすような仕掛けが大切である。
しかし、大津市が提唱しているまちづくり協議会の仕組みは、複雑化する地域課題に対応し、地域自らがその課題を解決していこうとする仕組みとして考えられているのかは疑問が残る。加えて、支所機能の見直しが同時に行われ、公民館をコミュニティセンター化して指定管理により運営していくこととされているが、どうもそこにしっかりと予算をつけていこうとするようには見受けられない。まちづくり協議会を安上がり下請け組織と捉え、押し付けようとしているようにも思われる。
滋賀県内の地域自治組織は必ずしもうまくいっているとは言えないが、その中で、まだうまくいっている感じがするのが草津市の方法である。地域への補助金を一括交付金化し、その後、支所機能を持つ市民センター・公民館をまちづくり協議会が指定管理者として運営する地域まちづくりセンターに再構築している。まちづくり協議会が雇用するセンター職員は数名配置され、その中から地域コーディネーターとして地域運営のキーパーソンとなる人が出てくることが期待されている。
大津市が草津市のようにていねいなステップを歩んでいれば、うまくいっていたかもしれないが、今の行政の動きや市民の反発を見る限り、どうもうまくいきそうにない。
ただ、市民も本当に支所が今のように維持できると思っているのだろうか。大津市の財政状況はよくないし、支所の統廃合は必要である。その上でのコミュニティセンター化も時代の要請でもある。でも、順番を間違うとうまくいかない。民主的な運営のできるまちづくり協議会を立ち上げてもらって、ベースとなる運営費を出し、それができあがった状況で市民センターのコミュニティセンター化を図って指定管理者制度を活用していればよい。
行政は、あまり焦らずに、しっかりとしたコンセプトを持ちながら、住民と話し合う姿勢が大切だ。
代表理事 阿部 圭宏
大津市はこれまで合併により市域を広げ、その結果として北部・中部・南部の微妙なバランスの上で市政運営が行われてきた。ハコモノも北部・中部・南部の3カ所に配置をすることで、市民の不満を抑えてきた面がある。同じように、地域の微妙なバランスという点では、学区(小学校区)も同様であり、学区単位に支所(市民センター)を置き、自治会が学区自治連合会や市自治連合会というピラミッド構造の中で運営されている面もある。2003年当時(志賀町と合併する前)の市のホームページでは、「大津市のまちづくりは、自治会組織を中心として活動の推進が図られ、大津市自治連合会は48年の歴史をもっています。 現在、市内には627の単位自治会を基本に31学区自治連合会、市自治連合会連携のもとに地域住民の連帯感が培われ、会員相互の親睦活動、地域活動が活発に展開されています」と紹介され、大津市が自治会に力点を置いてきたことが伺える。
2006年には大津市市民活動センターが開設され、行政が市民活動・NPOとの関係性を少し構築する場面も見られるようになったが、基本的には、自治会、自治連合会中心に据えた市政運営がなされてきたことは疑い得ない事実である。
2000年の地方分権一括法の施行を機に、全国で合併の嵐が吹くようになる。合併による市域の拡大に対して、住民に身近な自治の仕組みをつくる動きも活発になっていく。滋賀においても、合併した湖南市、東近江市、長浜市、甲賀市では、地域自治組織として、まちづくり協議会、地域づくり協議会、自治振興会という名称で動き出すが、大津市では全くこうした気運が醸成されてこなかった。自治会加入率は、2007年に70%を割り込み、2018年4月には、60.2%にまで落ち込んでいる。自治会中心主義を掲げられなくなり、次の手段を探る必要があった。そこで、遅ればせながら出てきたのが、支所機能の見直しと地域自治の仕組みとしてのまちづくり協議会である。
自治会加入率の減少は、その連合体である自治連合会を含めた統治機構の正統性に関わる問題である。少なくとも、自治連合会はこれまでのような地域を代表する組織とは強弁できなくなっている。それを補完するものとして、大津市が提案しているのがまちづくり協議会である。なぜ必要なのか、どのようにつくるべきか、運営はどうするのかなど、実際にはなかなか大変であり、行政がていねいに地域への説明を行い、地域の自発性、やる気を起こすような仕掛けが大切である。
しかし、大津市が提唱しているまちづくり協議会の仕組みは、複雑化する地域課題に対応し、地域自らがその課題を解決していこうとする仕組みとして考えられているのかは疑問が残る。加えて、支所機能の見直しが同時に行われ、公民館をコミュニティセンター化して指定管理により運営していくこととされているが、どうもそこにしっかりと予算をつけていこうとするようには見受けられない。まちづくり協議会を安上がり下請け組織と捉え、押し付けようとしているようにも思われる。
滋賀県内の地域自治組織は必ずしもうまくいっているとは言えないが、その中で、まだうまくいっている感じがするのが草津市の方法である。地域への補助金を一括交付金化し、その後、支所機能を持つ市民センター・公民館をまちづくり協議会が指定管理者として運営する地域まちづくりセンターに再構築している。まちづくり協議会が雇用するセンター職員は数名配置され、その中から地域コーディネーターとして地域運営のキーパーソンとなる人が出てくることが期待されている。
大津市が草津市のようにていねいなステップを歩んでいれば、うまくいっていたかもしれないが、今の行政の動きや市民の反発を見る限り、どうもうまくいきそうにない。
ただ、市民も本当に支所が今のように維持できると思っているのだろうか。大津市の財政状況はよくないし、支所の統廃合は必要である。その上でのコミュニティセンター化も時代の要請でもある。でも、順番を間違うとうまくいかない。民主的な運営のできるまちづくり協議会を立ち上げてもらって、ベースとなる運営費を出し、それができあがった状況で市民センターのコミュニティセンター化を図って指定管理者制度を活用していればよい。
行政は、あまり焦らずに、しっかりとしたコンセプトを持ちながら、住民と話し合う姿勢が大切だ。
Posted by しがNPOセンター at
09:00
│シリーズ【阿部コラム】