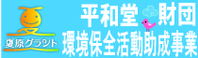2017年11月01日
選挙制度
しがNPOセンター
代表理事 阿部 圭宏
衆議院選挙が終わった。結果に対するいろいろな見方があると思うが、今回は、選挙制度について考えてみたい。
90年代の政治改革は、大きく選挙制度と政治資金とに大別できる。選挙制度の改革は海部内閣、宮沢内閣と議論され、94年の細川連立内閣ですったもんだの挙句、現行の小選挙区比例代表並立制と政党助成金の仕組みができた。
それまでの中選挙区制は、選挙に多くの金がかかり、議員定数にも不均衡があることが指摘され、派閥政治の問題もあって、リクルート事件をきっかけに改革論議が始まった。小選挙区制度の導入は、政治に金がかからなくなり、政権交代を容易にするという利点があると主張された。しかし、この制度だと、少数政党が生き残れないということもあり、復活当選による救済を含んだ小選挙区比例代表並立制が採用された。
小選挙区比例代表制が採用されて20年を経過し、今回を含めて8回の総選挙が行われているが、この間に多くの問題点が噴出している。まず、当初から指摘されてきた小選挙区での得票率と議席数との乖離である。時事通信の報道によると、今回の総選挙の小選挙289区で、自民党の得票率が48.2%に対し、議席占有率は75.4%に当たる218議席を獲得している。半数以上の投票が死票となっているという見方もできる。加えて、白票や無効票が多いという報道もある。
また、一票の格差については、最高裁が違憲状態を認定し、格差を是正するように促していることもあり、都道府県の定数是正や選挙区の区割り変更をしなければならない状況が続いている。有権者にとっても、区割りが変更されれば、馴染みのない候補者への投票を余儀なくされることも起こっている。
比例代表についても問題がある。名簿は政党が作成するので、例えば、政党は支持していても嫌いな人が名簿上位にいれば、投票することで当選してしまうジレンマがある。さらに、小選挙区との重複立候補を認めていることから、小選挙区で落選した人が復活することが当たり前になっているし、名簿順位が上位であれば、得票率が低くても当選していまうという逆転現象も起こっている。
では、選挙制度をどのようにすればよいのか。かつての中選挙区制度に戻せとか、完全比例選挙制度にしろとかいう意見も多いが、事はそう単純ではないようにも思われる。
中選挙区制度の復活は、55年体制への逆戻りという側面もあるし、もう一つ気になる点が、一票の格差である。都道府県単位に3〜5名程度の選挙区を置く場合、小選挙区と同じような一票の格差に配慮した区割りの難しさがある。
一方、比例代表制であるが、死票は少なくなるという点では有権者の意向に沿うと言える。しかし、政党を選ぶという今の衆議院の仕組みを使うと、これまで候補者個人を選んできたこの国の選挙制度を根底から変えてしまうこととなり、すんなりと受け入れられるかどうか分からない。確かに参議院のような政党名・候補者名のいずれでもよいという方法はあるかもしれないが、そうすると、候補者の当落の決定方法をどうするのかとか、今の全国11ブロックをどの単位で行うかなどの問題も出てくる。
このように、選挙制度は議論するとなかなか難しい。これを議員や一部の専門家だけで都合のよい形で決めることは問題がある。実際に、国民一人ひとりが有権者として投票することは憲法で保障された権利であることから、国民的な議論にしていくことが必要と思われる。制度改正に向けた多面的な議論に期待したい。
代表理事 阿部 圭宏
衆議院選挙が終わった。結果に対するいろいろな見方があると思うが、今回は、選挙制度について考えてみたい。
90年代の政治改革は、大きく選挙制度と政治資金とに大別できる。選挙制度の改革は海部内閣、宮沢内閣と議論され、94年の細川連立内閣ですったもんだの挙句、現行の小選挙区比例代表並立制と政党助成金の仕組みができた。
それまでの中選挙区制は、選挙に多くの金がかかり、議員定数にも不均衡があることが指摘され、派閥政治の問題もあって、リクルート事件をきっかけに改革論議が始まった。小選挙区制度の導入は、政治に金がかからなくなり、政権交代を容易にするという利点があると主張された。しかし、この制度だと、少数政党が生き残れないということもあり、復活当選による救済を含んだ小選挙区比例代表並立制が採用された。
小選挙区比例代表制が採用されて20年を経過し、今回を含めて8回の総選挙が行われているが、この間に多くの問題点が噴出している。まず、当初から指摘されてきた小選挙区での得票率と議席数との乖離である。時事通信の報道によると、今回の総選挙の小選挙289区で、自民党の得票率が48.2%に対し、議席占有率は75.4%に当たる218議席を獲得している。半数以上の投票が死票となっているという見方もできる。加えて、白票や無効票が多いという報道もある。
また、一票の格差については、最高裁が違憲状態を認定し、格差を是正するように促していることもあり、都道府県の定数是正や選挙区の区割り変更をしなければならない状況が続いている。有権者にとっても、区割りが変更されれば、馴染みのない候補者への投票を余儀なくされることも起こっている。
比例代表についても問題がある。名簿は政党が作成するので、例えば、政党は支持していても嫌いな人が名簿上位にいれば、投票することで当選してしまうジレンマがある。さらに、小選挙区との重複立候補を認めていることから、小選挙区で落選した人が復活することが当たり前になっているし、名簿順位が上位であれば、得票率が低くても当選していまうという逆転現象も起こっている。
では、選挙制度をどのようにすればよいのか。かつての中選挙区制度に戻せとか、完全比例選挙制度にしろとかいう意見も多いが、事はそう単純ではないようにも思われる。
中選挙区制度の復活は、55年体制への逆戻りという側面もあるし、もう一つ気になる点が、一票の格差である。都道府県単位に3〜5名程度の選挙区を置く場合、小選挙区と同じような一票の格差に配慮した区割りの難しさがある。
一方、比例代表制であるが、死票は少なくなるという点では有権者の意向に沿うと言える。しかし、政党を選ぶという今の衆議院の仕組みを使うと、これまで候補者個人を選んできたこの国の選挙制度を根底から変えてしまうこととなり、すんなりと受け入れられるかどうか分からない。確かに参議院のような政党名・候補者名のいずれでもよいという方法はあるかもしれないが、そうすると、候補者の当落の決定方法をどうするのかとか、今の全国11ブロックをどの単位で行うかなどの問題も出てくる。
このように、選挙制度は議論するとなかなか難しい。これを議員や一部の専門家だけで都合のよい形で決めることは問題がある。実際に、国民一人ひとりが有権者として投票することは憲法で保障された権利であることから、国民的な議論にしていくことが必要と思われる。制度改正に向けた多面的な議論に期待したい。
Posted by しがNPOセンター at
11:34
│シリーズ【阿部コラム】