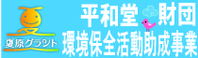2018年05月28日
2018年度総会とNPO法施行20周年記念パネルディスカッション 終了しました
 5月20日、しがNPOセンター2018年度総会と、NPO法施行20周年記念パネルディスカッション「NPOの20年と、これから」を行い、無事終了しました。
5月20日、しがNPOセンター2018年度総会と、NPO法施行20周年記念パネルディスカッション「NPOの20年と、これから」を行い、無事終了しました。総会では、会員の方からの貴重なご意見もいただき充実したものとなりました。ありがとうございます。
その後のパネルディスカッションでは、3団体3様の活動とふり返りをお聞きして、20年という時の流れの重さを感じるひとときでした。
コーディネーターは、しがNPOセンター 代表理事 阿部圭宏です。阿部はNPO法の前から滋賀県のNPOを支援してきました。
特定非営利活動法人 NPO子どもネットワークセンター天気村 事務局長 辻充子さん「滋賀県で最初に法人化しました。お金をもらって事業をするなら法人化しないと!と私が言って山田代表を説得。やはり法人化して雇用の安定性を図り社会保障をきちんとさせたかったのです。」
認定特定非営利活動法人 NPOぽぽハウス 副理事長 福井久美子さん「介護保険法を勉強しよう、というワーキンググループから任意団体へ、でもどうしても行政からは区別されます。そこで法人化しました。法人なら助成金や委託事業をとれますから。」
特定非営利活動法人 碧いびわ湖 代表理事 村上悟さん「環境生協の事業を2009年私が30才の時、引き継ぎました。あたたかい心ある会員の皆さんに接して、これならやっていける、と思い決めました。こういう経緯を持つNPO法人は他にないでしょう。」
阿部からの最後の質問は「今後の課題は?」
碧いびわ湖 村上さん「展望があるから課題があると思っていて、活動をもっと地域に落とし込んでいきたいと考えています。」
NPO子どもネットワークセンター天気村 辻さん「経済です。行政との関係性が協働で変わることを期待していたのですが変わりませんでした。今ある事業を大切に、もっと提案していきたいです」
NPOぽぽハウス 福井さん「ハローワークから就職してきた人と立ち上げ前からのスタッフではミッションが共有できません。ある程度仕事を覚えると新しい職場に変わってしまいます。うちの事業を担う人を育てていくのが課題です」
NPO法人設立当時の貴重なお話が聞け、これからのこともお聞きできました。登壇してくださった皆さま、ご来場くださった皆さま、ありがとうございました!
Posted by しがNPOセンター at
15:13
│しがNPOセンターの事業
2018年05月24日
2017年度 事業報告と決算書類
2018年5月20日、認定特定非営利活動法人 しがNPOセンターの総会を開催し、
2017年度の事業報告ならびに決算報告を行いました。その報告の詳しい内容は報告書をダウンロードしてご覧ください。
しがNPOセンターは、設立から9年、法人化7年を迎えました。2016年度に編集した『次世代に伝えたい 滋賀の市民活動史』を多くの方に読んでいただきたいと、本年度は販売に力を入れてきました。本冊子の販売を通じて、NPOのエンパワーの必要性を改めて感じています。
特に重点をおいて取り組んできた第Ⅱ期「NPO若人エンパワープロジェクト」は、6名の受講生が無事終了を迎えることができました。2年目は、講座やワークショップなどを通じての学びに加え、助成金を付けた企画事業に取り組んでもらいました。スタッフがメンターとして受講生を伴走支援することで、受講生の育ちを確認しながら、所属団体の基盤強化へもつながってきています。また参加メンバーからは、「こういう機会があったからこそ、違った分野の人たちと出会えました。貴重な体験ができました」との感想がありました。単発ではなく2年間という時間をかけ、互いの事業の進捗状況や課題などを共有しながら進めたことでの連帯感も高まったのではないかと感じています。助成金を付けて基盤強化のための企画事業を実施するプログラムを継続していくには課題は多いのですが、何らかの形で、これからを担う若いNPOスタッフのための事業について検討していきたいと考えています。
草津市の協働コーディネート業務は、まちづくり協議会が地域まちづくりセンターの指定管理になったことで、次のステージを迎えました。これまでの市民活動の支援や協働のところが手薄になってきていることを踏まえ、次年度への課題を残しています。
環境保全助成金事業「夏原グラント」は、立ち上げ間もない団体や、規模の小さい団体等の活動に対するファーストステップ助成を新たに始めました。これまでの助成を、一般助成という名称にして、引き続き最長3年継続助成の仕組みを維持しながら、それを終えた団体を支援する仕組みとしてステップアップ助成も実施しました。しがNPOセンターの強みを生かして、助成を受けた団体が継続・発展していけるように、講座や相談会、個別コンサルティングにも対応してきました。平和堂財団からは、中間支援組織が入っていることで、助成を受けている団体との関係性が構築できていること、団体や活動の情報が収集できていること、活動中の問題解決や組織運営のサポートができていることなどを評価していただいています。
災害ボランティアコーディネート事業の中では、連合愛のカンパの助成で実施した「災害ボランティアコーディネーター養成講座」が3回目の実施(最終年)となり、計112名が受講したことになります。3年間の実施を通じ、その間にも全国各地で災害が発生する中で新たな課題や取り組み方法への問いかけなど、状況は刻々と変化しています。そういったことも含め、今後も何らかの仕組みを用意する必要性を感じました。受講者には、しがNPOセンターが事務局を担っている「災害支援市民ネットワークしが」への参加を呼びかけ、多くの参加を得ています。昨年発生した熊本地震に対しては、近畿ろうきんのNPOパートナーシップ制度を使って支援を行うとともに、九州北部豪雨災害では、募金活動を行いました。
今年度実施した講座「障がい福祉サービス事業を行っているNPO法人のための税務セミナー」は、有料相談で対応した団体からの思いで実現したものです。講座開催当日は、団体の運営に直接かかわる問題でもあり、参加者の熱を感じました。今まで講座やセミナーなどは、しがNPOセンターから選定したテーマで開催してきたのですが、今回のように現場からの声に応えた形の効果の大きさを感じました。今後も、常にアンテナを巡らせながら、必要とされる内容で開催していきたいと考えています。
↓2017年度事業報告書
 (PDF: 427.49KB)
(PDF: 427.49KB)
↓2017年度決算書類
 (PDF: 1152.81KB)
(PDF: 1152.81KB)
2017年度の事業報告ならびに決算報告を行いました。その報告の詳しい内容は報告書をダウンロードしてご覧ください。
2017年度 事業報告書
2017年4月1日~2018年3月31日
概 要
2017年4月1日~2018年3月31日
概 要
しがNPOセンターは、設立から9年、法人化7年を迎えました。2016年度に編集した『次世代に伝えたい 滋賀の市民活動史』を多くの方に読んでいただきたいと、本年度は販売に力を入れてきました。本冊子の販売を通じて、NPOのエンパワーの必要性を改めて感じています。
特に重点をおいて取り組んできた第Ⅱ期「NPO若人エンパワープロジェクト」は、6名の受講生が無事終了を迎えることができました。2年目は、講座やワークショップなどを通じての学びに加え、助成金を付けた企画事業に取り組んでもらいました。スタッフがメンターとして受講生を伴走支援することで、受講生の育ちを確認しながら、所属団体の基盤強化へもつながってきています。また参加メンバーからは、「こういう機会があったからこそ、違った分野の人たちと出会えました。貴重な体験ができました」との感想がありました。単発ではなく2年間という時間をかけ、互いの事業の進捗状況や課題などを共有しながら進めたことでの連帯感も高まったのではないかと感じています。助成金を付けて基盤強化のための企画事業を実施するプログラムを継続していくには課題は多いのですが、何らかの形で、これからを担う若いNPOスタッフのための事業について検討していきたいと考えています。
草津市の協働コーディネート業務は、まちづくり協議会が地域まちづくりセンターの指定管理になったことで、次のステージを迎えました。これまでの市民活動の支援や協働のところが手薄になってきていることを踏まえ、次年度への課題を残しています。
環境保全助成金事業「夏原グラント」は、立ち上げ間もない団体や、規模の小さい団体等の活動に対するファーストステップ助成を新たに始めました。これまでの助成を、一般助成という名称にして、引き続き最長3年継続助成の仕組みを維持しながら、それを終えた団体を支援する仕組みとしてステップアップ助成も実施しました。しがNPOセンターの強みを生かして、助成を受けた団体が継続・発展していけるように、講座や相談会、個別コンサルティングにも対応してきました。平和堂財団からは、中間支援組織が入っていることで、助成を受けている団体との関係性が構築できていること、団体や活動の情報が収集できていること、活動中の問題解決や組織運営のサポートができていることなどを評価していただいています。
災害ボランティアコーディネート事業の中では、連合愛のカンパの助成で実施した「災害ボランティアコーディネーター養成講座」が3回目の実施(最終年)となり、計112名が受講したことになります。3年間の実施を通じ、その間にも全国各地で災害が発生する中で新たな課題や取り組み方法への問いかけなど、状況は刻々と変化しています。そういったことも含め、今後も何らかの仕組みを用意する必要性を感じました。受講者には、しがNPOセンターが事務局を担っている「災害支援市民ネットワークしが」への参加を呼びかけ、多くの参加を得ています。昨年発生した熊本地震に対しては、近畿ろうきんのNPOパートナーシップ制度を使って支援を行うとともに、九州北部豪雨災害では、募金活動を行いました。
今年度実施した講座「障がい福祉サービス事業を行っているNPO法人のための税務セミナー」は、有料相談で対応した団体からの思いで実現したものです。講座開催当日は、団体の運営に直接かかわる問題でもあり、参加者の熱を感じました。今まで講座やセミナーなどは、しがNPOセンターから選定したテーマで開催してきたのですが、今回のように現場からの声に応えた形の効果の大きさを感じました。今後も、常にアンテナを巡らせながら、必要とされる内容で開催していきたいと考えています。
↓2017年度事業報告書
↓2017年度決算書類
2018年05月24日
「新書de読書会」 第19回のお知らせ
第19回の課題本は「縮小ニッポンの衝撃」です。
これはNHKスペシャル取材班によって作られた本です。テレビ番組で同じ内容で放送されたのを見た覚えがあります。
人口減少社会は日本にとって経験したことのない社会。どうなっていくのでしょうか?
ご参加をお待ちしています。
■開催日時:2018年6月18日(月)
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました!
■課題本:「縮小ニッポンの衝撃 」 NHKスペシャル取材班(講談社現代新書)
■開催時間:19:00 ~ 21:00
■会場:草津市立まちづくりセンター304
■参加のルール
①課題本をご持参ください。読み切っていなくても結構です。
②積極的に発言しましょう。
③意見への反論はOK、でも否定や誹謗中傷などはNG。
④読書会中の画像をネット上への公開する場合、参加者へ了解をとりましょう。
■進め方
しがNPOセンターの代表理事・阿部圭宏が進行します。
本全体の感想やキーワードを深めての議論を予定します。
話の展開によっては、本から離れた話題にも花が咲くこともあります。
■参加費
500円
■参加申込み
参加を希望される方は準備の都合等がありますので、下記をメールにてお知らせください。
申し込みがなくても、当日飛び入り参加OKです。
1・参加者名、所属
2・連絡先(当日連絡がとれる携帯電話番号などをお教えください)
■お問い合わせ・申込先
認定特定非営利活動法人しがNPOセンター
TEL:0748-34-3033 FAX:020-4664-3933
E-mail:shiga.npo@gmail.com
■今後の予定
第20回7月9日「敗者の想像力」加藤典洋(集英社新書)
第21回8月20日「これからの日本、これからの教育」前川喜平・寺脇研(ちくま新書)
第22回9月10日「『歴史認識』とは何か」大沼保昭(中公新書)
これはNHKスペシャル取材班によって作られた本です。テレビ番組で同じ内容で放送されたのを見た覚えがあります。
人口減少社会は日本にとって経験したことのない社会。どうなっていくのでしょうか?
ご参加をお待ちしています。
■開催日時:2018年6月18日(月)
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました!
■課題本:「縮小ニッポンの衝撃 」 NHKスペシャル取材班(講談社現代新書)
■開催時間:19:00 ~ 21:00
■会場:草津市立まちづくりセンター304
■参加のルール
①課題本をご持参ください。読み切っていなくても結構です。
②積極的に発言しましょう。
③意見への反論はOK、でも否定や誹謗中傷などはNG。
④読書会中の画像をネット上への公開する場合、参加者へ了解をとりましょう。
■進め方
しがNPOセンターの代表理事・阿部圭宏が進行します。
本全体の感想やキーワードを深めての議論を予定します。
話の展開によっては、本から離れた話題にも花が咲くこともあります。
■参加費
500円
■参加申込み
参加を希望される方は準備の都合等がありますので、下記をメールにてお知らせください。
申し込みがなくても、当日飛び入り参加OKです。
1・参加者名、所属
2・連絡先(当日連絡がとれる携帯電話番号などをお教えください)
■お問い合わせ・申込先
認定特定非営利活動法人しがNPOセンター
TEL:0748-34-3033 FAX:020-4664-3933
E-mail:shiga.npo@gmail.com
■今後の予定
第20回7月9日「敗者の想像力」加藤典洋(集英社新書)
第21回8月20日「これからの日本、これからの教育」前川喜平・寺脇研(ちくま新書)
第22回9月10日「『歴史認識』とは何か」大沼保昭(中公新書)
2018年05月16日
「新書de読書会」 第18回のお知らせ
第18回の課題本は「“町内会”は義務ですか?~コミュニティーの自由と実践~」です。
町内会・自治会を「辞めたい」「抜けたい」と思った方は多いのでは? 地域によっては切実な問題となっているかもしれません。
ご参加をお待ちしています。
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました!
こんなことが話題になりました。
---------------------------
町内会は地域性や規模、歴史など違いが大きいし、行政との関わりも千差万別。そのような町内会をひとくくりでは語れないけれども、多くが他の町内会のことを知らないのは間違いなさそうです。知らなければ改革は難しいでしょう。現状に流されることなく、「何のため」「誰のため」なのかを考えて話し合うことが初めの一歩なのかもしれません。
---------------------------
■開催日時:2018年5月21日(月)
■課題本:「“町内会”は義務ですか?~コミュニティーの自由と実践~」紙屋高雪(小学館新書)
■開催時間:19:00 ~ 21:00
■会場:草津市立まちづくりセンター304
■参加のルール
①課題本をご持参ください。読み切っていなくても結構です。
②積極的に発言しましょう。
③意見への反論はOK、でも否定や誹謗中傷などはNG。
④読書会中の画像をネット上への公開する場合、参加者へ了解をとりましょう。
■進め方
しがNPOセンターの代表理事・阿部圭宏が進行します。
本全体の感想やキーワードを深めての議論を予定します。
話の展開によっては、本から離れた話題にも花が咲くこともあります。
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました!
■参加費
500円
■参加申込み
参加を希望される方は準備の都合等がありますので、下記をメールにてお知らせください。
申し込みがなくても、当日飛び入り参加OKです。
1・参加者名、所属
2・連絡先(当日連絡がとれる携帯電話番号などをお教えください)
■お問い合わせ・申込先
認定特定非営利活動法人しがNPOセンター
TEL:0748-34-3033 FAX:020-4664-3933
E-mail:shiga.npo@gmail.com
■今後の予定
第19回6月18日「縮小ニッポンの衝撃 」 NHKスペシャル取材班(講談社現代新書)
第20回7月9日「敗者の想像力」加藤典洋(集英社新書)
第21回8月20日「これからの日本、これからの教育」前川喜平・寺脇研(ちくま新書)
町内会・自治会を「辞めたい」「抜けたい」と思った方は多いのでは? 地域によっては切実な問題となっているかもしれません。
ご参加をお待ちしています。
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました!
こんなことが話題になりました。
---------------------------
町内会は地域性や規模、歴史など違いが大きいし、行政との関わりも千差万別。そのような町内会をひとくくりでは語れないけれども、多くが他の町内会のことを知らないのは間違いなさそうです。知らなければ改革は難しいでしょう。現状に流されることなく、「何のため」「誰のため」なのかを考えて話し合うことが初めの一歩なのかもしれません。
---------------------------
■開催日時:2018年5月21日(月)
■課題本:「“町内会”は義務ですか?~コミュニティーの自由と実践~」紙屋高雪(小学館新書)
■開催時間:19:00 ~ 21:00
■会場:草津市立まちづくりセンター304
■参加のルール
①課題本をご持参ください。読み切っていなくても結構です。
②積極的に発言しましょう。
③意見への反論はOK、でも否定や誹謗中傷などはNG。
④読書会中の画像をネット上への公開する場合、参加者へ了解をとりましょう。
■進め方
しがNPOセンターの代表理事・阿部圭宏が進行します。
本全体の感想やキーワードを深めての議論を予定します。
話の展開によっては、本から離れた話題にも花が咲くこともあります。
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました!
■参加費
500円
■参加申込み
参加を希望される方は準備の都合等がありますので、下記をメールにてお知らせください。
申し込みがなくても、当日飛び入り参加OKです。
1・参加者名、所属
2・連絡先(当日連絡がとれる携帯電話番号などをお教えください)
■お問い合わせ・申込先
認定特定非営利活動法人しがNPOセンター
TEL:0748-34-3033 FAX:020-4664-3933
E-mail:shiga.npo@gmail.com
■今後の予定
第19回6月18日「縮小ニッポンの衝撃 」 NHKスペシャル取材班(講談社現代新書)
第20回7月9日「敗者の想像力」加藤典洋(集英社新書)
第21回8月20日「これからの日本、これからの教育」前川喜平・寺脇研(ちくま新書)
2018年05月01日
情報リテラシー
しがNPOセンター
代表理事 阿部 圭宏
私事で恐縮だが、昨年からツイッターを再開した。それまでは、フェイスブックを多用していたのだが、やはり迅速に情報を得るには、ツイッターの方が圧倒的に便利だという判断による。140字という限られた文字数での情報発信とは言え、そこに書かれた内容を確認しながら、落とし込んでいく作業が自分に合っているように思う。ただ、他のユーザーのツイート(つぶやき)を自分のアカウントから再発信する「リツイート」が多いので、フォローしていただいている方には迷惑かもしれない。
ツイッターやフェイスブックをやっていると、2つの媒体の違いに気づく。フェイスブックは基本的に実名だが、ツイッターは匿名の方が多い。フェイスブックは近況報告や友達同士での話題のやりとりのような感覚だが、ツイッターではキャラクターを作っての投稿という場合もあるので、双方を使い分けている方も多い。使い勝手や好き嫌いなどで、一方しか利用していない人もいる。
当然、ツイッターやフェイスブックには、投稿のルールがあり、それに違反するとアカウントの凍結、停止ということになりかねない。特にツイッターの場合は、過激な投稿も多く、誹謗・中傷であったり、あるいは、フェイクとも思われるような投稿もある。ネットだから気軽に投稿してしまうこともあるのかもしれないが、場合によっては、アカウントの凍結だけでなく、犯罪として捜査の対象となったり、民事で損害賠償請求をされる場合もある。
これは何も投稿した方だけの話ではない。投稿をリツイートした人にも同じような責任が伴う。ただ、実際にリツイートした人には、そんな意識は少ないだろう。だから平気でできるとも言える。一方的な反対意見の人を貶める投稿が、何万回もリツイートされているという現実もある。最近の例では、財務省の事務次官のセクハラ問題だ。本当がどうかは分からないが、被害を受けたとされる記者の名前がネットで拡散されるとともに、ここに輪をかけた投稿がなされて、まさに二次被害という現象が起こっている。
ネットでの情報をそのまま信じてとんでもないことを投稿するというのでは、この情報化時代に遅れてしまう。膨大な情報の中から必要な情報を抜き出し、活用する能力を持つこと、すなわち、情報リテラシーが求められている。そのためには、ネット以外の情報、新聞、雑誌、単行本などを読み比べ、自分としての理解を深めるしか道はないように思われる。
代表理事 阿部 圭宏
私事で恐縮だが、昨年からツイッターを再開した。それまでは、フェイスブックを多用していたのだが、やはり迅速に情報を得るには、ツイッターの方が圧倒的に便利だという判断による。140字という限られた文字数での情報発信とは言え、そこに書かれた内容を確認しながら、落とし込んでいく作業が自分に合っているように思う。ただ、他のユーザーのツイート(つぶやき)を自分のアカウントから再発信する「リツイート」が多いので、フォローしていただいている方には迷惑かもしれない。
ツイッターやフェイスブックをやっていると、2つの媒体の違いに気づく。フェイスブックは基本的に実名だが、ツイッターは匿名の方が多い。フェイスブックは近況報告や友達同士での話題のやりとりのような感覚だが、ツイッターではキャラクターを作っての投稿という場合もあるので、双方を使い分けている方も多い。使い勝手や好き嫌いなどで、一方しか利用していない人もいる。
当然、ツイッターやフェイスブックには、投稿のルールがあり、それに違反するとアカウントの凍結、停止ということになりかねない。特にツイッターの場合は、過激な投稿も多く、誹謗・中傷であったり、あるいは、フェイクとも思われるような投稿もある。ネットだから気軽に投稿してしまうこともあるのかもしれないが、場合によっては、アカウントの凍結だけでなく、犯罪として捜査の対象となったり、民事で損害賠償請求をされる場合もある。
これは何も投稿した方だけの話ではない。投稿をリツイートした人にも同じような責任が伴う。ただ、実際にリツイートした人には、そんな意識は少ないだろう。だから平気でできるとも言える。一方的な反対意見の人を貶める投稿が、何万回もリツイートされているという現実もある。最近の例では、財務省の事務次官のセクハラ問題だ。本当がどうかは分からないが、被害を受けたとされる記者の名前がネットで拡散されるとともに、ここに輪をかけた投稿がなされて、まさに二次被害という現象が起こっている。
ネットでの情報をそのまま信じてとんでもないことを投稿するというのでは、この情報化時代に遅れてしまう。膨大な情報の中から必要な情報を抜き出し、活用する能力を持つこと、すなわち、情報リテラシーが求められている。そのためには、ネット以外の情報、新聞、雑誌、単行本などを読み比べ、自分としての理解を深めるしか道はないように思われる。
Posted by しがNPOセンター at
09:05
│シリーズ【阿部コラム】