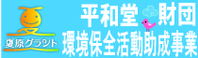2016年12月26日
年末年始のお休みについて
日頃はお世話になり、ありがとうございます。
しがNPOセンターの年末年始のお休みは以下の通りです。
1月5日(木)から通常通り営業です。
2017年もどうぞよろしくお願いいたします。
2016年12月29日(木)~ 2017年1月4日(水)
2017年1月4日(水)
しがNPOセンターの年末年始のお休みは以下の通りです。
1月5日(木)から通常通り営業です。
2017年もどうぞよろしくお願いいたします。
2016年12月29日(木)~
 2017年1月4日(水)
2017年1月4日(水) 2016年12月08日
「新書de読書会」 第5回のお知らせ
「新書de読書会」がもうすぐ!
身近でありながら、お葬式や行事以外では訪れない場所になっている「寺」。
現代の寺はどうあるべきなのか?
今回の課題本は「寺よ、変われ」高橋卓志(岩波新書)です!
お気軽にご参加を。お待ちしています。
※この読書会は終了しました。ありがとうございました!次回にご期待ください
■開催日時:2016年12月19日(月)
■課題本:「寺よ、変われ」高橋卓志(岩波新書)
■開催時間:19:00 ~ 21:00
■会場:草津市立まちづくりセンター
■参加のルール
①課題本をご持参ください。読み切っていなくても結構です。
②積極的に発言しましょう。
③意見への反論はOK、でも否定や誹謗中傷などはNG。
④読書会中の画像をネット上への公開する場合、参加者へ了解をとりましょう。
■進め方
しがNPOセンターの代表理事・阿部圭宏が進行します。
本全体の感想やキーワードを深めての議論を予定します。
話の展開によっては、本から離れた話題にも花が咲くこともあります。
■参加費
500円
■参加申込み
参加を希望される方は準備の都合等がありますので、下記をメールにてお知らせください。
申し込みがなくても、当日飛び入り参加OKです。
1・参加者名、所属
2・連絡先(当日連絡がとれる携帯電話番号などをお教えください)
■お問い合わせ・申込先
認定特定非営利活動法人しがNPOセンター
TEL&FAX 0748-34-3033
E-mail shiga.npo@gmail.com
■今後の予定
2017年
第6回2月20日「自治体崩壊」田村秀(イースト新書) ※←前回の読書会は終了しました。ありがとうございました!第6回にご期待ください
第7回4月17日「里山資本主義」藻谷浩介・NHK広島取材班(角川ONEテーマ21)
第8回5月15日「市民の政治学~討議デモクラシーとは何か~」篠原一(岩波新書)
身近でありながら、お葬式や行事以外では訪れない場所になっている「寺」。
現代の寺はどうあるべきなのか?
今回の課題本は「寺よ、変われ」高橋卓志(岩波新書)です!
お気軽にご参加を。お待ちしています。
※この読書会は終了しました。ありがとうございました!次回にご期待ください
■開催日時:2016年12月19日(月)
■課題本:「寺よ、変われ」高橋卓志(岩波新書)
■開催時間:19:00 ~ 21:00
■会場:草津市立まちづくりセンター
■参加のルール
①課題本をご持参ください。読み切っていなくても結構です。
②積極的に発言しましょう。
③意見への反論はOK、でも否定や誹謗中傷などはNG。
④読書会中の画像をネット上への公開する場合、参加者へ了解をとりましょう。
■進め方
しがNPOセンターの代表理事・阿部圭宏が進行します。
本全体の感想やキーワードを深めての議論を予定します。
話の展開によっては、本から離れた話題にも花が咲くこともあります。
■参加費
500円
■参加申込み
参加を希望される方は準備の都合等がありますので、下記をメールにてお知らせください。
申し込みがなくても、当日飛び入り参加OKです。
1・参加者名、所属
2・連絡先(当日連絡がとれる携帯電話番号などをお教えください)
■お問い合わせ・申込先
認定特定非営利活動法人しがNPOセンター
TEL&FAX 0748-34-3033
E-mail shiga.npo@gmail.com
■今後の予定
2017年
第6回2月20日「自治体崩壊」田村秀(イースト新書) ※←前回の読書会は終了しました。ありがとうございました!第6回にご期待ください
第7回4月17日「里山資本主義」藻谷浩介・NHK広島取材班(角川ONEテーマ21)
第8回5月15日「市民の政治学~討議デモクラシーとは何か~」篠原一(岩波新書)
2016年12月02日
チャリティーイベントの難しさ
しがNPOセンター 代表理事
阿部圭宏
チャリティーコンサートやチャリティーランなど、身近なチャリティーを呼称するイベントが、日本でも定着してきている。
日本でチャリティー番組をうたう最大規模のイベントは、日本テレビ系の『24時間テレビ 「愛は地球を救う」』であろう。感動を与えるという評価と裏腹に、多分にショー化しすぎているなどの批判もあるが、今回はそうした内容ではなく、お金のことを考えてみたい。
公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会(全国31社の放送事業者による組織)のホームページを見ると、24時間テレビでの今年の寄付金総額は8億8千万円を超えている。こうした寄付金は、24時間テレビチャリティー委員会が、経費を一切差し引くことなく全額、公益目的事業としての福祉・環境・災害復興の3分野の支援活動に活用するとされている。
寄付金は全額支援活動に使われているので問題はないのだが、少し気になることもある。テレビ番組なので制作費がかかるが、こうしたことは情報公開されていない。中には、出演者へのギャラはどうなっているのかを知りたいと思う人もいるだろう。少しでも役に立てばということで寄付をした人にとっては、例えば出演者にギャラが多く支払われていた場合には、何となく割り切れない気持ちになることもあるかもしれない。
チャリティーは、そもそも慈愛・博愛・同胞愛または慈善の精神に基づいて行われる公益的な活動・行為もしくはそれを行う組織のことだとされる。社会的な弱者に対する福祉的な支援活動、災害に対する支援活動などがよく知られたチャリティー活動であるが、社会に対する貢献全般がチャリティーであるとも言える。
こうしたチャリティーに係る費用は募金や寄付でまかなわれることが多いため、その運営には透明性が求められる。寄付した人が割り切れない気持ちになるのは、まさに情報がしっかりと公開されないことにある。
災害支援のための身近なチャリティーイベントをやっているある団体のホームページを見ると、イベントでの収益金で被災地の団体を継続的に支援している。例えば、コンサートの収益金を寄付したと書いているが、そのコンサートでは実際にどれだけの収入があり、経費がかかったのかがホームページを見ている限り分からない。出演しているアーティストはプロなのか、アマチュアなのかも含めて気になる。しかも、支援先の団体は、フェイスブックを通じて、自分たちの活動を報告しているものの、収支が明らかにされていないため、その団体にどれだけ寄付が集まっているのかも皆目分からない。
寄付は、寄付してくれる方にどれだけ共感していただけるかによっていると言っても過言ではない。寄付した人に少しでも疑念や不安を与えるようでは、寄付を受けたり、チャリティー活動を主催する資格がないのではないか。自分たちの活動、会計、組織運営をしっかりと見てもらうことに努力していくようになりたいものだ。
阿部圭宏
チャリティーコンサートやチャリティーランなど、身近なチャリティーを呼称するイベントが、日本でも定着してきている。
日本でチャリティー番組をうたう最大規模のイベントは、日本テレビ系の『24時間テレビ 「愛は地球を救う」』であろう。感動を与えるという評価と裏腹に、多分にショー化しすぎているなどの批判もあるが、今回はそうした内容ではなく、お金のことを考えてみたい。
公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会(全国31社の放送事業者による組織)のホームページを見ると、24時間テレビでの今年の寄付金総額は8億8千万円を超えている。こうした寄付金は、24時間テレビチャリティー委員会が、経費を一切差し引くことなく全額、公益目的事業としての福祉・環境・災害復興の3分野の支援活動に活用するとされている。
寄付金は全額支援活動に使われているので問題はないのだが、少し気になることもある。テレビ番組なので制作費がかかるが、こうしたことは情報公開されていない。中には、出演者へのギャラはどうなっているのかを知りたいと思う人もいるだろう。少しでも役に立てばということで寄付をした人にとっては、例えば出演者にギャラが多く支払われていた場合には、何となく割り切れない気持ちになることもあるかもしれない。
チャリティーは、そもそも慈愛・博愛・同胞愛または慈善の精神に基づいて行われる公益的な活動・行為もしくはそれを行う組織のことだとされる。社会的な弱者に対する福祉的な支援活動、災害に対する支援活動などがよく知られたチャリティー活動であるが、社会に対する貢献全般がチャリティーであるとも言える。
こうしたチャリティーに係る費用は募金や寄付でまかなわれることが多いため、その運営には透明性が求められる。寄付した人が割り切れない気持ちになるのは、まさに情報がしっかりと公開されないことにある。
災害支援のための身近なチャリティーイベントをやっているある団体のホームページを見ると、イベントでの収益金で被災地の団体を継続的に支援している。例えば、コンサートの収益金を寄付したと書いているが、そのコンサートでは実際にどれだけの収入があり、経費がかかったのかがホームページを見ている限り分からない。出演しているアーティストはプロなのか、アマチュアなのかも含めて気になる。しかも、支援先の団体は、フェイスブックを通じて、自分たちの活動を報告しているものの、収支が明らかにされていないため、その団体にどれだけ寄付が集まっているのかも皆目分からない。
寄付は、寄付してくれる方にどれだけ共感していただけるかによっていると言っても過言ではない。寄付した人に少しでも疑念や不安を与えるようでは、寄付を受けたり、チャリティー活動を主催する資格がないのではないか。自分たちの活動、会計、組織運営をしっかりと見てもらうことに努力していくようになりたいものだ。
Posted by しがNPOセンター at
15:42
│シリーズ【阿部コラム】