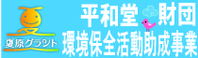2019年06月21日
夏原グラント環境保全活動団体交流会のお知らせ
夏原グラント環境保全活動団体交流会
2019年7月27日(土)13:15〜16:45
内容:情報やノウハウを交換したり、ネットワークを広げるための交流会です。
・夏原グラント運営委員によるキーワードリレートーク
・テーブル交流2回
①分野別 ②課題別
会場:草津市立まちづくりセンター
定員:先着80名・要申込
参加:無料
対象:京都府内、滋賀県内で
環境保全活動をしているNPO法人
市民活動団体、学生団体
環境保全に関心のある方
■ 夏原グラントとは
豊かな環境の保全および創造のために、市民活動団体・学生団体が自主的に行う活動で、先進的な他のモデルとなる事業に対して公益財団法人平和堂財団が、助成するものです。「琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動」で、滋賀県内・京都府内で実施される水質保全、森林・里山保全、水源の森保全、河川や湖等の環境保全、生物多様性維持等が対象です。
【夏原グラント主催】 公益財団法人 平和堂財団
【運営事務局】 認定特定非営利活動法人 しがNPOセンター
------------------------------------
■メール・FAXの方はこちらをご利用ください。
送り先:FAX:020-4664-3933 メール:shiga.npo@gmail.com
◆7月27日(土)夏原グラント団体交流会に申し込みます
お名前 (ふりがな):
ご住所(個人の方のみ) 〒
所属団体名:
ご連絡のつきやすい電話:
mail(受付のご連絡用):
FAX:
------------------------------------
■ オンライン入力フォームからも お申込いただけます
2019年7月27日(土)13:15〜16:45
内容:情報やノウハウを交換したり、ネットワークを広げるための交流会です。
・夏原グラント運営委員によるキーワードリレートーク
・テーブル交流2回
①分野別 ②課題別
会場:草津市立まちづくりセンター
定員:先着80名・要申込
参加:無料
対象:京都府内、滋賀県内で
環境保全活動をしているNPO法人
市民活動団体、学生団体
環境保全に関心のある方
■ 夏原グラントとは
豊かな環境の保全および創造のために、市民活動団体・学生団体が自主的に行う活動で、先進的な他のモデルとなる事業に対して公益財団法人平和堂財団が、助成するものです。「琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動」で、滋賀県内・京都府内で実施される水質保全、森林・里山保全、水源の森保全、河川や湖等の環境保全、生物多様性維持等が対象です。
【夏原グラント主催】 公益財団法人 平和堂財団
【運営事務局】 認定特定非営利活動法人 しがNPOセンター
------------------------------------
■メール・FAXの方はこちらをご利用ください。
送り先:FAX:020-4664-3933 メール:shiga.npo@gmail.com
◆7月27日(土)夏原グラント団体交流会に申し込みます
お名前 (ふりがな):
ご住所(個人の方のみ) 〒
所属団体名:
ご連絡のつきやすい電話:
mail(受付のご連絡用):
FAX:
------------------------------------
■ オンライン入力フォームからも お申込いただけます
2019年06月18日
「新書de読書会」 第32回のお知らせ
「新書de読書会」 第32回の課題本は「日本が売られる」です。
「水と安全はタダ同然、医療と介護は世界トップ。そんな日本に今、とんでもない魔の手が伸びているのを知っているだろうか?」幻冬舎サイトより引用
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
■開催日時:2019年7月22日(月)
■課題本:「日本が売られる」堤未果(幻冬舎新書)
■開催時間:19:00 ~ 21:00
■会場:草津市立まちづくりセンター304
■参加のルール
①課題本をご持参ください。読み切っていなくても結構です。
②積極的に発言しましょう。
③意見への反論はOK、でも否定や誹謗中傷などはNG。
④読書会中の画像をネット上への公開する場合、参加者へ了解をとりましょう。
■進め方
しがNPOセンターの代表理事・阿部圭宏が進行します。阿部以外の参加者が課題本を選定したときには、その方が進行します。
本全体の感想やキーワードを深めての議論を予定します。
話の展開によっては、本から離れた話題にも花が咲くこともあります。
■参加費
500円
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
■参加申込み
参加を希望される方は準備の都合等がありますので、下記をメールにてお知らせください。
申し込みがなくても、当日飛び入り参加OKです。
1・参加者名、所属
2・連絡先(当日連絡がとれる携帯電話番号などをお教えください)
■お問い合わせ・申込先
認定特定非営利活動法人しがNPOセンター
TEL:0748-34-3033 FAX:020-4664-3933
E-mail:shiga.npo@gmail.com
■今後の予定
第33回8月19日 「移民クライシス」出井康博(角川新書)
第34回9月 9日 「地方議会を再生する」相川俊英(集英社新書)
「水と安全はタダ同然、医療と介護は世界トップ。そんな日本に今、とんでもない魔の手が伸びているのを知っているだろうか?」幻冬舎サイトより引用
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
■開催日時:2019年7月22日(月)
■課題本:「日本が売られる」堤未果(幻冬舎新書)
■開催時間:19:00 ~ 21:00
■会場:草津市立まちづくりセンター304
■参加のルール
①課題本をご持参ください。読み切っていなくても結構です。
②積極的に発言しましょう。
③意見への反論はOK、でも否定や誹謗中傷などはNG。
④読書会中の画像をネット上への公開する場合、参加者へ了解をとりましょう。
■進め方
しがNPOセンターの代表理事・阿部圭宏が進行します。阿部以外の参加者が課題本を選定したときには、その方が進行します。
本全体の感想やキーワードを深めての議論を予定します。
話の展開によっては、本から離れた話題にも花が咲くこともあります。
■参加費
500円
※この回は終了しました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
■参加申込み
参加を希望される方は準備の都合等がありますので、下記をメールにてお知らせください。
申し込みがなくても、当日飛び入り参加OKです。
1・参加者名、所属
2・連絡先(当日連絡がとれる携帯電話番号などをお教えください)
■お問い合わせ・申込先
認定特定非営利活動法人しがNPOセンター
TEL:0748-34-3033 FAX:020-4664-3933
E-mail:shiga.npo@gmail.com
■今後の予定
第33回8月19日 「移民クライシス」出井康博(角川新書)
第34回9月 9日 「地方議会を再生する」相川俊英(集英社新書)
2019年06月17日
災害ボランティアコーディネーター実践講座のお知らせ
災害ボランティアコーディネーター実践講座
災害の現場で活動したことのある方から、
経験のない初心者まで、さまざまな方を交えて
災害現場で使える実践講座です。
いますぐ使えるスキルとノウハウを、この講座で身につけましょう!!
皆さまのご参加をお待ちしています。
日 時:8月24日(土)13:30~17:00
会 場:滋賀県県民交流センター303
講 師:石井布紀子さん(NPO法人さくらネット代表理事)
テーマ:テーマ:「災害が起こったときに、支援する仕組みを考えよう」
参加費:お一人1,000円(税込)
対 象:どなたでも
募集定員:30人先着順
主催:認定特定非営利活動法人し が N P O セ ン タ ー
共催:災害支援市民ネットワークしが・近畿ろうきん地域共生推進室
※この事業は「近畿ろうきんNPOパートナーシップ」からの協力で実施しています。
■石井布紀子さんプロフィール
1995年に発生した阪神淡路大震災の際に被災し、被災地での要援護者支援などに関わり始める。その後、研修の講師や兵庫県・内閣府他のさまざまの会議の委員・アドバイザーを経て、現在は地域福祉の視点に立つ防災・減災の取り組みを推進している。2005年から赤い羽根の中央共同募金会が設置する災害ボランティア活動支援プロジェクト会議の幹事および共同事務局。また、2012年から「1.17防災未来賞ぼうさい甲子園」事務局を担っている。現在、NPO法人さくらネット代表理事、一般社団法人子どものエンパワメントいわて理事。
■<お申込み方法>
PC・スマホからのお申込みフォームも可能です。
フォームに必要事項を記入し、メール・FAXで下記宛先にどうぞ。
メールの件名は「災害VC実践講座申込み」としてください。
FAX:020-4664-3933 E-mail: shiga.npo@gmail.com
------------<キリトリ>------------
■8/24(土)災害ボランティアコーディネーター実践講座 お申込みフォーム
お名前: (ふりがな)
所属団体名(あれば):
ご連絡のつきやすい電話:
mail:
FAX(メールのない方):
ご住所:〒
------------<キリトリ>------------
↓オンライン入力フォーム
災害の現場で活動したことのある方から、
経験のない初心者まで、さまざまな方を交えて
災害現場で使える実践講座です。
いますぐ使えるスキルとノウハウを、この講座で身につけましょう!!
皆さまのご参加をお待ちしています。
日 時:8月24日(土)13:30~17:00
会 場:滋賀県県民交流センター303
講 師:石井布紀子さん(NPO法人さくらネット代表理事)
テーマ:テーマ:「災害が起こったときに、支援する仕組みを考えよう」
参加費:お一人1,000円(税込)
対 象:どなたでも
募集定員:30人先着順
主催:認定特定非営利活動法人し が N P O セ ン タ ー
共催:災害支援市民ネットワークしが・近畿ろうきん地域共生推進室
※この事業は「近畿ろうきんNPOパートナーシップ」からの協力で実施しています。
■石井布紀子さんプロフィール
1995年に発生した阪神淡路大震災の際に被災し、被災地での要援護者支援などに関わり始める。その後、研修の講師や兵庫県・内閣府他のさまざまの会議の委員・アドバイザーを経て、現在は地域福祉の視点に立つ防災・減災の取り組みを推進している。2005年から赤い羽根の中央共同募金会が設置する災害ボランティア活動支援プロジェクト会議の幹事および共同事務局。また、2012年から「1.17防災未来賞ぼうさい甲子園」事務局を担っている。現在、NPO法人さくらネット代表理事、一般社団法人子どものエンパワメントいわて理事。
■<お申込み方法>
PC・スマホからのお申込みフォームも可能です。
フォームに必要事項を記入し、メール・FAXで下記宛先にどうぞ。
メールの件名は「災害VC実践講座申込み」としてください。
FAX:020-4664-3933 E-mail: shiga.npo@gmail.com
------------<キリトリ>------------
■8/24(土)災害ボランティアコーディネーター実践講座 お申込みフォーム
お名前: (ふりがな)
所属団体名(あれば):
ご連絡のつきやすい電話:
mail:
FAX(メールのない方):
ご住所:〒
------------<キリトリ>------------
↓オンライン入力フォーム
2019年06月03日
大学のこれから
しがNPOセンター
代表理事 阿部 圭宏
文部科学省の2018年度学校基本調査によると、大学(学部)の進学率は53.3%となっている。2009年度に初めて5割を超えた進学率は、ここ10年堅調に推移している。大学進学率が高いことにより、日本の高等教育の未来が、必ずしも輝いているとは言えない。
最近の大学をめぐる状況をいくつか列挙する。
まず、奨学金問題から。返済が必要な日本学生支援機構の奨学金を借りている学生は半数近くになるそうだ。就職すると、直ちに返済が始まり、返済が滞ると、厳しい取り立てが行われ、返済の滞納は社会問題化している。奨学金という名前を借りた教育ローンが学生に重くのしかかっている。
なぜ、多くの学生が借りているかと言えば、国公立大学の授業料が上がっていることもその要因に挙げられよう。
一方で、国立大学は独立法人化されて、国からの運営交付金が毎年1%ずつカットされている。その影響は、教員数に影響を与えていて、退職者があっても補充せず、非正規教員を充てるということが行われている。大学の自治はどこにもなく、ますます文部科学省の支配が強まり、競争資金は一部の大学に集中し、地域人材を供給してきた地方国立大学は存亡の危機に晒されている。このような中で、防衛装備庁が2015年度から開始した「安全保障技術研究推進制度」による研究費に手を挙げる人たちが出てくるなどの問題が出ている。
東京大学に関する話題もいくつかある。これまで東京大学の文系でもっとも難易度が高いとされてきたのが文科一類(法学部)であるが、今年は合格者の平均点が文科二類(経済学部)のほうが高かった。優秀な人材は官僚になってという時代ではないらしい。最近は、東大法学部を出ても、外資系企業に就職する人が多いそうだ。国のためより、手っ取り早く金でということでの文化二類志望だろうか。東大生の親の62.7%が年収950万円以上だという統計もあり、本人の能力に加え、恵まれた学習環境が進学に影響していることも間違いのない事実であり、ここにも格差は生まれている。
しかし、東京大学は、イギリスの高等教育専門誌「THE(Times Higher Education)」が発表した2019年「THE世界大学ランキング」では、前回より順位を上げたものの42位で、京都大学は62位だった。アジアでは、中国の台頭が目立ち、日本の大学の大半は依然として衰退、あるいは静止状態と評価されている。
日本の場合、教育を取り巻く環境は厳しい。高等教育に限らず、教育費の国庫負担は極端に低いため、個人の負担が大きい。福祉と同じで、教育も自己責任という感じが強く、社会で教育環境を整えるという発想にならない。リカレントも含めて教育に力を入れている国は、いろんな意味で将来性がある。増税があっても、教育という目に見える形でのサービス提供があれば、誰もが納得するはずだ。
今後、日本の大学は少子化の影響を受けて、縮小していかざるを得ないが、将来を見据えたビジョンを誰が示せるのか。一人ひとりが真剣に考えないと本当に沈没する。
代表理事 阿部 圭宏
文部科学省の2018年度学校基本調査によると、大学(学部)の進学率は53.3%となっている。2009年度に初めて5割を超えた進学率は、ここ10年堅調に推移している。大学進学率が高いことにより、日本の高等教育の未来が、必ずしも輝いているとは言えない。
最近の大学をめぐる状況をいくつか列挙する。
まず、奨学金問題から。返済が必要な日本学生支援機構の奨学金を借りている学生は半数近くになるそうだ。就職すると、直ちに返済が始まり、返済が滞ると、厳しい取り立てが行われ、返済の滞納は社会問題化している。奨学金という名前を借りた教育ローンが学生に重くのしかかっている。
なぜ、多くの学生が借りているかと言えば、国公立大学の授業料が上がっていることもその要因に挙げられよう。
一方で、国立大学は独立法人化されて、国からの運営交付金が毎年1%ずつカットされている。その影響は、教員数に影響を与えていて、退職者があっても補充せず、非正規教員を充てるということが行われている。大学の自治はどこにもなく、ますます文部科学省の支配が強まり、競争資金は一部の大学に集中し、地域人材を供給してきた地方国立大学は存亡の危機に晒されている。このような中で、防衛装備庁が2015年度から開始した「安全保障技術研究推進制度」による研究費に手を挙げる人たちが出てくるなどの問題が出ている。
東京大学に関する話題もいくつかある。これまで東京大学の文系でもっとも難易度が高いとされてきたのが文科一類(法学部)であるが、今年は合格者の平均点が文科二類(経済学部)のほうが高かった。優秀な人材は官僚になってという時代ではないらしい。最近は、東大法学部を出ても、外資系企業に就職する人が多いそうだ。国のためより、手っ取り早く金でということでの文化二類志望だろうか。東大生の親の62.7%が年収950万円以上だという統計もあり、本人の能力に加え、恵まれた学習環境が進学に影響していることも間違いのない事実であり、ここにも格差は生まれている。
しかし、東京大学は、イギリスの高等教育専門誌「THE(Times Higher Education)」が発表した2019年「THE世界大学ランキング」では、前回より順位を上げたものの42位で、京都大学は62位だった。アジアでは、中国の台頭が目立ち、日本の大学の大半は依然として衰退、あるいは静止状態と評価されている。
日本の場合、教育を取り巻く環境は厳しい。高等教育に限らず、教育費の国庫負担は極端に低いため、個人の負担が大きい。福祉と同じで、教育も自己責任という感じが強く、社会で教育環境を整えるという発想にならない。リカレントも含めて教育に力を入れている国は、いろんな意味で将来性がある。増税があっても、教育という目に見える形でのサービス提供があれば、誰もが納得するはずだ。
今後、日本の大学は少子化の影響を受けて、縮小していかざるを得ないが、将来を見据えたビジョンを誰が示せるのか。一人ひとりが真剣に考えないと本当に沈没する。
Posted by しがNPOセンター at
09:05
│シリーズ【阿部コラム】