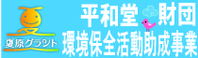2017年02月08日
第2回研究会「今、子供たちにどんな防災教育が必要なのか」報告
2月8日(水)「災害支援市民ネットワークしが」の第2回研究会を開催しました。
「今、子供たちにどんな防災教育が必要なのか」をテーマに、NPO法人さくらネットの河田のどかさんにお話をしていただきました。

「どんな防災教育が必要なのか」の前に「なぜ必要なのか」からわかりやすく説いてくださいます。
「地震はあまりないから」「川から離れているから」「ここは高台だから」。でも何かのきっかけで「この地」を離れることがあります。引越し、進学、就職、結婚・・・。どのようなところにいても、「備えていれば、守れる命がある」「みんなで助かるために、みんなで取り組む」が大切だとのことです。
地域と学校が一緒になって取り組んでいる事例の紹介があり、とても参考になりました。

後半はワークショップ。
子供たちとのワークショップでされているものを模擬的に行います。
災害時に持ち出すものを考えてみると、人によって違うことを知ることができました。
これからも災害支援市民ネットワークしがでは、研究会など開催していく予定です。
興味のある方ならどなたでもご参加いただけます。ぜひ、ご一緒に災害に備えましょう。
「今、子供たちにどんな防災教育が必要なのか」をテーマに、NPO法人さくらネットの河田のどかさんにお話をしていただきました。

「どんな防災教育が必要なのか」の前に「なぜ必要なのか」からわかりやすく説いてくださいます。
「地震はあまりないから」「川から離れているから」「ここは高台だから」。でも何かのきっかけで「この地」を離れることがあります。引越し、進学、就職、結婚・・・。どのようなところにいても、「備えていれば、守れる命がある」「みんなで助かるために、みんなで取り組む」が大切だとのことです。
地域と学校が一緒になって取り組んでいる事例の紹介があり、とても参考になりました。

後半はワークショップ。
子供たちとのワークショップでされているものを模擬的に行います。
災害時に持ち出すものを考えてみると、人によって違うことを知ることができました。
これからも災害支援市民ネットワークしがでは、研究会など開催していく予定です。
興味のある方ならどなたでもご参加いただけます。ぜひ、ご一緒に災害に備えましょう。
Posted by しがNPOセンター at
16:42
│災害支援市民ネットワークしが
2017年02月01日
トランプ政権誕生から考える
しがNPOセンター 代表理事
阿部圭宏
世界を賑わせているトランプがアメリカ大統領に就任した。選挙戦での過激な発言、就任前の記者会見でのメディアとの対立、就任時の最低支持率、企業への恫喝、就任早々に大統領令の連発など、話題には事欠かない。難民らの入国拒否という大統領令により、空港で入国を拒否されたり、拘束されたりする事態まで起こってしまっている。トランプ現象とは何なのかは、これまでにも多くの評論が出されているし、今後も出され続けるだろう。トランフは日本や世界にとって救世主なのか、あるいは撹乱要因なのかはよく分からないが、そもそも、そういう評価の次元の話ではないのかもしれない。
トランプが支持される要因は、そのポピュリズム手法だ。ポピュリズムという言葉は多義的だが、ここでは、大衆迎合主義(=政治に関して理性的に判断する知的な市民よりも、情緒や感情によって態度を決める大衆を重視し、その支持を求める手法)という意味を当てると分かりやすい。今の政治に不満を持つ大衆の心をつかむ。具体的には、不法移民に仕事を奪われるからメキシコとの国境に巨大な壁を作るとか、アメリカ企業の海外移転を制限するとかの主張である。同様の主張は、イギリスのEU離脱やヨッローパでの極右勢力の台頭とも重なっている。
ポピュリズムは、今や、民主主義にとって避けがたい現象となっている。日本においても、小泉政権以降、ポピュリズムが一般化している。これは自民党だけではなく、民主党政権のときもそうであったし、国政だけではなく、大阪の橋下徹についても同様のことが言える。郵政民営化では、賛成か反対かとの二項対立を争点として選挙に圧勝した。民主主義の根幹である多数決による決定の不備を補おうと、中身をじっくりと問いながら議論するという形をとらず、短絡的に決定して物事を進めていく手法とも言える。
政治が一部エリートに乗っ取られていることへの不満、マスコミがまさに権力として能書きを垂れることへの不信、学者のような知的権威者に対する疑問などが相まって、現在政治が動いている。結果として、権力に物言わないマスコミ、権力にすり寄る学者、政策議論を大切にしない政治家などが跋扈し、民主的手続きを否定する動きになっている。得か損かという面ばかりが強調され、政治が経済的な価値観に回収されてしまい、意思決定方法は、内田樹が指摘するように株式会社化していく姿を見ているようだ。
日本を含め、これからの世界がどのようになっていくか、不安を抱く人は多いだろう。不安や不満を抱える人が多い社会は、ますます不安定になっていく。アメリカだけが大変なのではなく、我が国の状況も非常に危ない。こういう時代だからこそ、我々は、もう一度、民主主義の理想を築き上げるための方策を考えていく必要がある。身近な政治に関心を持ち、不満だけを表出するのではなく、小さな実践から築き上げていくしかないのではないだろうか。
阿部圭宏
世界を賑わせているトランプがアメリカ大統領に就任した。選挙戦での過激な発言、就任前の記者会見でのメディアとの対立、就任時の最低支持率、企業への恫喝、就任早々に大統領令の連発など、話題には事欠かない。難民らの入国拒否という大統領令により、空港で入国を拒否されたり、拘束されたりする事態まで起こってしまっている。トランプ現象とは何なのかは、これまでにも多くの評論が出されているし、今後も出され続けるだろう。トランフは日本や世界にとって救世主なのか、あるいは撹乱要因なのかはよく分からないが、そもそも、そういう評価の次元の話ではないのかもしれない。
トランプが支持される要因は、そのポピュリズム手法だ。ポピュリズムという言葉は多義的だが、ここでは、大衆迎合主義(=政治に関して理性的に判断する知的な市民よりも、情緒や感情によって態度を決める大衆を重視し、その支持を求める手法)という意味を当てると分かりやすい。今の政治に不満を持つ大衆の心をつかむ。具体的には、不法移民に仕事を奪われるからメキシコとの国境に巨大な壁を作るとか、アメリカ企業の海外移転を制限するとかの主張である。同様の主張は、イギリスのEU離脱やヨッローパでの極右勢力の台頭とも重なっている。
ポピュリズムは、今や、民主主義にとって避けがたい現象となっている。日本においても、小泉政権以降、ポピュリズムが一般化している。これは自民党だけではなく、民主党政権のときもそうであったし、国政だけではなく、大阪の橋下徹についても同様のことが言える。郵政民営化では、賛成か反対かとの二項対立を争点として選挙に圧勝した。民主主義の根幹である多数決による決定の不備を補おうと、中身をじっくりと問いながら議論するという形をとらず、短絡的に決定して物事を進めていく手法とも言える。
政治が一部エリートに乗っ取られていることへの不満、マスコミがまさに権力として能書きを垂れることへの不信、学者のような知的権威者に対する疑問などが相まって、現在政治が動いている。結果として、権力に物言わないマスコミ、権力にすり寄る学者、政策議論を大切にしない政治家などが跋扈し、民主的手続きを否定する動きになっている。得か損かという面ばかりが強調され、政治が経済的な価値観に回収されてしまい、意思決定方法は、内田樹が指摘するように株式会社化していく姿を見ているようだ。
日本を含め、これからの世界がどのようになっていくか、不安を抱く人は多いだろう。不安や不満を抱える人が多い社会は、ますます不安定になっていく。アメリカだけが大変なのではなく、我が国の状況も非常に危ない。こういう時代だからこそ、我々は、もう一度、民主主義の理想を築き上げるための方策を考えていく必要がある。身近な政治に関心を持ち、不満だけを表出するのではなく、小さな実践から築き上げていくしかないのではないだろうか。
Posted by しがNPOセンター at
09:29
│シリーズ【阿部コラム】