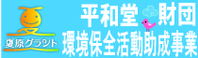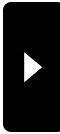2013年06月14日
吉里吉里海岸でこの夏イベント開催か!
ずっと現地で踏ん張ってこられたNGOのグッドネーバーズ・ジャパン。
この春、ついに大槌町からスタッフを引き揚げました。
私たちがカムバックサーモンプロジェクトと吉里吉里クリーン作戦でお世話になった、
武鑓さんも東京へ異動されました。
でも、時々大槌の方と出会っておられるご様子です。
そして、今日は現地からのニュースをお知らせいただきました。
↓グッドネーバーズ・ジャパンのフェイスブックページへリンク
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568255536560022&set=a.171136139605299.48289.170604462991800&type=1&theater
地元の方が中心となり、砂浜が復活したのを喜ぶ(?)イベントが
7月末に行われる予定だそうです。
1枚の写真と添えられたメッセージだけの情報なので、詳しいことは不明です。
また、グッドネーバーズ・ジャパンのフェイスブックページに追加情報が期待できそうなので、「いいね!」を押してフォローしておいてくださいね。
こちらでも情報がキャッチ出来次第、またアップいたします!!
この春、ついに大槌町からスタッフを引き揚げました。
私たちがカムバックサーモンプロジェクトと吉里吉里クリーン作戦でお世話になった、
武鑓さんも東京へ異動されました。
でも、時々大槌の方と出会っておられるご様子です。
そして、今日は現地からのニュースをお知らせいただきました。
↓グッドネーバーズ・ジャパンのフェイスブックページへリンク
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568255536560022&set=a.171136139605299.48289.170604462991800&type=1&theater
地元の方が中心となり、砂浜が復活したのを喜ぶ(?)イベントが
7月末に行われる予定だそうです。
1枚の写真と添えられたメッセージだけの情報なので、詳しいことは不明です。
また、グッドネーバーズ・ジャパンのフェイスブックページに追加情報が期待できそうなので、「いいね!」を押してフォローしておいてくださいね。
こちらでも情報がキャッチ出来次第、またアップいたします!!
2013年06月14日
報告 ホタルの学校
日曜日の夜、大津市南郷で行われている、ホタルの学校の皆さんの観察会に参加してきました。
夏原グラント 採択事業「みんなで守るホタルと川」の一環です。
※この記事は 夏原グラント 活動レポート でもっとたくさんの画像とともにご覧いただけます。

ホタルの学校の皆さんがフィールドにされているのは、大津市の南部、瀬田川の南郷荒堰より少し上流で瀬田川に流れ込む千丈川です。
この川に近い南郷市民センターで6月9日日曜日昼間に「ほたるの集い」が開催されました。
(「ほたるの集い」写真はホタルの学校の荒井さんよりご提供の予定)
「ほたるの集い」ではホタルの学校に参加して、千丈川の生きもの調べやホタルの観察の発表、そしてホタルや生きものクイズなどを行い、吹奏楽団による演奏など、地元の皆さんも多数ご参加され盛況だったそうです。
そして「ほたるの集い」の終了した後、夜7時40分からは同じく南郷市民センター前に集合し、千丈川でのホタル観察会が行われました。今回は観察会だけに参加させていただきました。
まずはホタルの学校代表の荒井紀子さんからあいさつと注意がありました。
「みなさん、こんばんは!これから、ホタルの観察に出かけます。今日は、
琵琶湖博物館から桝永先生と、野鳥が専門の天野先生、地元にお住まいの宮地先生が参加してくださっています。ホタルのことなど、わからないことがあったら聞いてください」
子どもと大人、20名くらいで出発しましたが、千丈川で待っている仲間や家族たち10人と合流して、
総勢30人で観察しました。
瀬田川沿いの車の交通量が多い道を少し歩き、千丈川へ向かいます。
参加する子どもは、必ず「ホタルパトロール」と大きく書かれた黄色いタスキを肩に掛け、手にはカウンターを持っています。
タスキがないと暗くてどこの誰か識別できません。カウンターは見つけたホタルの数を数えるための必須アイテムです。
瀬田川へ注ぐ河口あたりで、まずホタルの数を数えました。川の中のカヤの葉の間に光るホタル、ほわほわと光りながら飛ぶホタルがいます!
すると、川に面したお宅のお父さんがパジャマ姿で参加されました。
子どもが質問「昔はこの川にはどれくらいホタルがいたのですか?」
お父さん「昔は手でつかめるほどおったよ」
子どもたちが数えた数を報告し、記録しているところです。
上流に行くと、さらに観察できるホタルの数は増え、見物の人の数も多くなりました。
住宅地の中の小さな川に、こんなにホタルが見られるとは!
「みなさん、今、ホタルのオスが同時明滅していまーす!オスが草むらにいるメスにアピールしているところでーす!光って消えるまで2秒です。」と荒井さん。
まとめた結果をホタルの学校1期生で現在大学生の堀井さんがひとこと。
「昨年の8月の大水と今年の空梅雨で今年はホタルは少ないだろうと予測していましたが、今回観察された数は90~100匹以上でした。
昨年の雨の影響はあまりないのではないかと思われます」
ホタルの学校では、川のあちこちにこのようなポスターを設置して、ホタルのために環境美化をアピールしています。
また、活動はホタルの出る初夏だけでなく、一年を通じて行っています。
はぼ毎月の川の中の生きもの観察会、ホタルマップづくりとウォーターステーション琵琶で行われる「水辺の匠」イベントでの展示、琵琶湖博物館での昆虫採集、南郷学区文化フェスティバルでの展示発表、千丈川周辺のゴミ拾い、自然素材を使った工作、野鳥観察会などが予定されています。

これは伺った日の昼間に行われた、南郷フェスティバルでの発表風景です。
1期生から10年。今回のようにOB、OGが参加してくれることも多くなってきた、と代表の荒井さん。
地域の方々にも浸透している活動であることが感じられます。
ホタルを通じて地域の自然環境への意識の高い子どもたちが増え、自ら行動していくだろうと今後も楽しみです。
スタッフH
夏原グラント 採択事業「みんなで守るホタルと川」の一環です。
※この記事は 夏原グラント 活動レポート でもっとたくさんの画像とともにご覧いただけます。

ホタルの学校の皆さんがフィールドにされているのは、大津市の南部、瀬田川の南郷荒堰より少し上流で瀬田川に流れ込む千丈川です。
この川に近い南郷市民センターで6月9日日曜日昼間に「ほたるの集い」が開催されました。
(「ほたるの集い」写真はホタルの学校の荒井さんよりご提供の予定)
「ほたるの集い」ではホタルの学校に参加して、千丈川の生きもの調べやホタルの観察の発表、そしてホタルや生きものクイズなどを行い、吹奏楽団による演奏など、地元の皆さんも多数ご参加され盛況だったそうです。
そして「ほたるの集い」の終了した後、夜7時40分からは同じく南郷市民センター前に集合し、千丈川でのホタル観察会が行われました。今回は観察会だけに参加させていただきました。
まずはホタルの学校代表の荒井紀子さんからあいさつと注意がありました。
「みなさん、こんばんは!これから、ホタルの観察に出かけます。今日は、
琵琶湖博物館から桝永先生と、野鳥が専門の天野先生、地元にお住まいの宮地先生が参加してくださっています。ホタルのことなど、わからないことがあったら聞いてください」
子どもと大人、20名くらいで出発しましたが、千丈川で待っている仲間や家族たち10人と合流して、
総勢30人で観察しました。
瀬田川沿いの車の交通量が多い道を少し歩き、千丈川へ向かいます。
参加する子どもは、必ず「ホタルパトロール」と大きく書かれた黄色いタスキを肩に掛け、手にはカウンターを持っています。
タスキがないと暗くてどこの誰か識別できません。カウンターは見つけたホタルの数を数えるための必須アイテムです。
瀬田川へ注ぐ河口あたりで、まずホタルの数を数えました。川の中のカヤの葉の間に光るホタル、ほわほわと光りながら飛ぶホタルがいます!
すると、川に面したお宅のお父さんがパジャマ姿で参加されました。
子どもが質問「昔はこの川にはどれくらいホタルがいたのですか?」
お父さん「昔は手でつかめるほどおったよ」
子どもたちが数えた数を報告し、記録しているところです。
上流に行くと、さらに観察できるホタルの数は増え、見物の人の数も多くなりました。
住宅地の中の小さな川に、こんなにホタルが見られるとは!
「みなさん、今、ホタルのオスが同時明滅していまーす!オスが草むらにいるメスにアピールしているところでーす!光って消えるまで2秒です。」と荒井さん。
まとめた結果をホタルの学校1期生で現在大学生の堀井さんがひとこと。
「昨年の8月の大水と今年の空梅雨で今年はホタルは少ないだろうと予測していましたが、今回観察された数は90~100匹以上でした。
昨年の雨の影響はあまりないのではないかと思われます」
ホタルの学校では、川のあちこちにこのようなポスターを設置して、ホタルのために環境美化をアピールしています。
また、活動はホタルの出る初夏だけでなく、一年を通じて行っています。
はぼ毎月の川の中の生きもの観察会、ホタルマップづくりとウォーターステーション琵琶で行われる「水辺の匠」イベントでの展示、琵琶湖博物館での昆虫採集、南郷学区文化フェスティバルでの展示発表、千丈川周辺のゴミ拾い、自然素材を使った工作、野鳥観察会などが予定されています。

これは伺った日の昼間に行われた、南郷フェスティバルでの発表風景です。
1期生から10年。今回のようにOB、OGが参加してくれることも多くなってきた、と代表の荒井さん。
地域の方々にも浸透している活動であることが感じられます。
ホタルを通じて地域の自然環境への意識の高い子どもたちが増え、自ら行動していくだろうと今後も楽しみです。
スタッフH
2013年06月14日
Adobe製品のライセンス再入荷 TechSoup(テックスープ)
TechSoup(テックスープ)のソフトウェア寄贈の、
Adobe製品のライセンスが再入荷したとのメールニュースが届きました。
さっそく朝一番で申請!
折り返し認められたとのメールが届きました。
これで、消費税&手数料16,634 円を振り込めば、
あこがれのソフトのダウンロードができます。
これに先だってスタッフHは
NPO法人ユースビジョン主催のイラストレーター講座を受講しておきました。
満を持してのソフトダウンロード。楽しみです!
Adobe製品のライセンスが再入荷したとのメールニュースが届きました。
さっそく朝一番で申請!
折り返し認められたとのメールが届きました。
これで、消費税&手数料16,634 円を振り込めば、
あこがれのソフトのダウンロードができます。
これに先だってスタッフHは
NPO法人ユースビジョン主催のイラストレーター講座を受講しておきました。
満を持してのソフトダウンロード。楽しみです!
2013年06月11日
市民活動という言葉の持つ意味
しがNPOセンター副代表理事の阿部圭宏のコラムを毎月掲載することにいたしました。
熱い思いを持って、あるいは長い時間、
市民活動を続けていると、自分の団体と活動を客観視できなくなりがちです。
時には少し立ち止まって考えるひとときをどうぞ。
コラムに対するご意見や、今後のテーマのご要望などもお寄せくださるとうれしいです。
スタッフH
----------------------------------------------------------

しがNPOセンター 副代表理事
阿部圭宏
特定非営利活動促進法(いわゆる「NPO法」)が施行されたのが1998年12月1日であり、今年は15周年の節目を迎える。この間、NPOという言葉は社会に広く浸透してきた。NPOが広がったのはNPO法が社会的に認知されたからだ。しかし、NPO法が議論されていた当時は、NPOという言葉よりも市民活動とか市民活動団体という言葉のほうが関係者の間では一般的であった。
NPOは一般的には民間非営利組織と言われ、公益法人をベースとしつつ、社会福祉法人や学校法人、生活協同組合などの法人に加え、法人格を持たない任意団体を含めた非常に幅広い非営利の団体を意味してきた。一方、市民活動団体は、法人格の有無に関係なく、社会的課題を解決するために、市民が自主的・自発的に立ち上げた非営利の団体のことである。したがって、市民活動団体はNPOの一部だと言える。
NPO法は法案提出時、「市民活動促進法案」という法律名で、一定の要件を備えた市民活動団体に「市民活動法人」という法人格を付与し、そのことで市民活動を促進したいという意図があった。国会での法案審議過程で結局、法律名も変わり、「特定非営利活動法人」という名称が与えられることとなり、法案に込められた市民活動の促進という目的が曖昧化されてしまった感がある。しかも、特定非営利活動法人という名称の分かりにくさ、使いづらさなどを理由として、いつしか「NPO法人」と呼ばれるようになってしまった。それと軌を一にするように、市民活動団体という言葉もNPOという言葉に置き換わってしまったように思われる。
NPO法人制度の運用においては、市民活動と言えないものもそこに含まれている。法律の目的には、「市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動」という言い方がされているものの、市民活動とは違ったものもNPO法人格を付与されている。市民活動以外の非営利活動が広がることが悪いということではないが、一つ押さえておくべきことがある。それは、われわれが推進したいのは市民活動なのだということである。市民活動が意味する市民の自発性、先駆性、多様性などの特徴、あるいは市民活動の持つ運動性は、市民活動という言葉以外に十分に社会へ伝えられない。市民活動はあくまで市民活動なのであり、これをNPO活動などとは決して言い換えられないのだ。市民活動という言葉にこだわることは非常に大切だと思われる。
熱い思いを持って、あるいは長い時間、
市民活動を続けていると、自分の団体と活動を客観視できなくなりがちです。
時には少し立ち止まって考えるひとときをどうぞ。
コラムに対するご意見や、今後のテーマのご要望などもお寄せくださるとうれしいです。
スタッフH
----------------------------------------------------------

しがNPOセンター 副代表理事
阿部圭宏
特定非営利活動促進法(いわゆる「NPO法」)が施行されたのが1998年12月1日であり、今年は15周年の節目を迎える。この間、NPOという言葉は社会に広く浸透してきた。NPOが広がったのはNPO法が社会的に認知されたからだ。しかし、NPO法が議論されていた当時は、NPOという言葉よりも市民活動とか市民活動団体という言葉のほうが関係者の間では一般的であった。
NPOは一般的には民間非営利組織と言われ、公益法人をベースとしつつ、社会福祉法人や学校法人、生活協同組合などの法人に加え、法人格を持たない任意団体を含めた非常に幅広い非営利の団体を意味してきた。一方、市民活動団体は、法人格の有無に関係なく、社会的課題を解決するために、市民が自主的・自発的に立ち上げた非営利の団体のことである。したがって、市民活動団体はNPOの一部だと言える。
NPO法は法案提出時、「市民活動促進法案」という法律名で、一定の要件を備えた市民活動団体に「市民活動法人」という法人格を付与し、そのことで市民活動を促進したいという意図があった。国会での法案審議過程で結局、法律名も変わり、「特定非営利活動法人」という名称が与えられることとなり、法案に込められた市民活動の促進という目的が曖昧化されてしまった感がある。しかも、特定非営利活動法人という名称の分かりにくさ、使いづらさなどを理由として、いつしか「NPO法人」と呼ばれるようになってしまった。それと軌を一にするように、市民活動団体という言葉もNPOという言葉に置き換わってしまったように思われる。
NPO法人制度の運用においては、市民活動と言えないものもそこに含まれている。法律の目的には、「市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動」という言い方がされているものの、市民活動とは違ったものもNPO法人格を付与されている。市民活動以外の非営利活動が広がることが悪いということではないが、一つ押さえておくべきことがある。それは、われわれが推進したいのは市民活動なのだということである。市民活動が意味する市民の自発性、先駆性、多様性などの特徴、あるいは市民活動の持つ運動性は、市民活動という言葉以外に十分に社会へ伝えられない。市民活動はあくまで市民活動なのであり、これをNPO活動などとは決して言い換えられないのだ。市民活動という言葉にこだわることは非常に大切だと思われる。
Posted by しがNPOセンター at
10:22
│シリーズ【阿部コラム】
2013年06月08日
新しい公共支援事業が終了、滋賀県の成果に注目
2011・12年と、1億5千万円をかけた滋賀県の新しい公共支援事業が終了し、運営委員との懇談会が数回にわけて県庁で行われていましたが、昨日この最終日が終わり、しがNPOセンターも参加しました。基盤整備事業、県モデル事業、市町モデル事業、合わせて約30事業の報告と意見交換、お疲れさまでした。(内容の概要は下記のサイトへ)
また下記のサイトで後日運営委員会からの報告があろうと思いますが、課題はこれらの事業をどう継続させるかです。実施したNPOは2年間で、次の資金繰り・展開を考えて実施せざるを得なかったというのが現実ですし、初めからそれを見越して取り組むというのがこの事業のポイント。 行政との協働事業による税金の投入や各協議体からの分担金の確保以外に、自主事業での増収の見通しや、新たな資金の集め方(融資・寄付など)にも目が向いてきたというのも成果だろうと思います。県・各市町の事業につきましては、皆様も応援を・・・。NPOだけでなく、関わった県や市町の今後の施策にも注目です。
しがNPOセンターでは、県内で事業継続しつづけるNPOのための基盤整備事業として、講座・相談・認定相談窓口事業を行いました。これらの事業は、今年も続けて実施しますので、今後ともよろしくお願いします。(あたりまえですが、もちろん有料ですよ)
お問い合わせは、しがNPOセンターへ・・・・・・。
http://www.pref.shiga.lg.jp/c/katsudo/kyodonet/news/atarasikoukyou.html
また下記のサイトで後日運営委員会からの報告があろうと思いますが、課題はこれらの事業をどう継続させるかです。実施したNPOは2年間で、次の資金繰り・展開を考えて実施せざるを得なかったというのが現実ですし、初めからそれを見越して取り組むというのがこの事業のポイント。 行政との協働事業による税金の投入や各協議体からの分担金の確保以外に、自主事業での増収の見通しや、新たな資金の集め方(融資・寄付など)にも目が向いてきたというのも成果だろうと思います。県・各市町の事業につきましては、皆様も応援を・・・。NPOだけでなく、関わった県や市町の今後の施策にも注目です。
しがNPOセンターでは、県内で事業継続しつづけるNPOのための基盤整備事業として、講座・相談・認定相談窓口事業を行いました。これらの事業は、今年も続けて実施しますので、今後ともよろしくお願いします。(あたりまえですが、もちろん有料ですよ)
お問い合わせは、しがNPOセンターへ・・・・・・。
http://www.pref.shiga.lg.jp/c/katsudo/kyodonet/news/atarasikoukyou.html