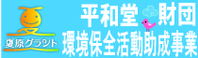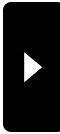2012年04月30日
事業の概要
●事業の目的
滋賀県には、関係団体と滋賀県からなる「滋賀県災害ボランティア活動連絡会」が設置され、平常時の活動としてマニュアルづくりや研修会の開催などが行われ、また、実際に滋賀で災害が起こった場合の災害ボランティアセンター設置への対応がされることとなっている。
今回の東日本大震災では、社会福祉協議会はブロック派遣で宮城へ職員を派遣したり、行政もそれぞれの立場での支援を行っている。連絡会の構成団体もそれぞれ独自に支援活動を行っているが、連絡会としてボランティアやNPOのサポートを積極的に行っていくような仕組みになっていない。
滋賀のNPOは、災害支援を体系的に行うノウハウを備えているところが少なく、また、今回の東日本大震災では、独自に被災地支援を行っているNPOもあるが、そうした情報が一元化されていない。
さらに、県内NPOの災害対応の情報も把握できていないため、実際に滋賀で災害が起こった場合、協働型の災害ボランティアセンターの設置がスムーズにいかないことが予想される。

こうした現状を踏まえ、NPOの東日本大震災での被災支援活動状況やNPOとしての災害支援メニューのデータベース化を図ることにより、NPO側の災害対応スキルを磨くとともに、連絡会とNPOとの連携構築を図る。
加えて、NPOとして被災地支援を行いたいが、単独では支援活動ができない団体も多く、そうしたNPOの思いを実際の支援活動につなげる。
●事業内容
5本柱で事業を実施する。
1)滋賀NPO災害ボランティアネットワークの構築
・NPOの災害ボランティアネットワーク構築のための検討会議(滋賀県社会福祉協議会、中間支援N
POなどで構成する会議体)を運営する。
・「滋賀県災害ボランティア活動連絡会」とNPOとの連携調整をする。
・他自治体におけるネットワーク事例の調査を行う。
2)NPOの災害支援データベースの作成
・県内NPOに対し、災害支援メニューづくりのための調査を行い、データベース化する。
・あわせて、東日本大震災への支援活動の調査も行う。
3)東日本大震災被災地支援活動
・ボランティアバスを被災地へ派遣する(NPOの特徴を活かし、災害支援メニューで挙がってきた中か
ら、検討会議で選定したプロジェクトを組んで行う)
4)報告会・成果フォーラムの開催(3月)
5.)NPO災害ネットワークの構築
・滋賀県外のNPOとのネットワークの構築を検討する。
4,業務の具体的な進め方と手順 (案)
1)滋賀NPO災害ボランティアネットワークの構築
・会議体であるネットワーク構築会議を行う。「滋賀NPO災害ボランティアネットワーク構築会議」を意思決
定機関として本事業を実施する。事務局はしがNPOセンターが担う。
・会議体の名簿作成をしつつ、さらに団体を拡大していく。情報共有の方法なども考える。
・事例調査を行う。他地域のNPO災害ネットワークの事例など。
2)NPOの災害支援データベースの作成
・調査を行うデータベース化する。被災支援プロジェクトへとつなげていく。
会議体で、データベース項目の検討なども行う。
3)東日本大震災被災地支援活動
・被災地支援プロジェクトの検討
会議体メンバーや、NPOからの発案により検討する。
バスに限らず、予算内で必要に応じて動く。
4)報告会・成果フォーラムの開催(3月)
・東日本大震災の支援活動報告会を1年目に行った。2年目(今年度)には最終的な成果をまとめるフォーラムを
開催する。
5)NPO災害ネットワークの構築
・滋賀県外のNPOとのネットワークの構築を検討する。
他地域の活動の調査
他地域の活動への参加
他地域の活動へのリンク など
滋賀県には、関係団体と滋賀県からなる「滋賀県災害ボランティア活動連絡会」が設置され、平常時の活動としてマニュアルづくりや研修会の開催などが行われ、また、実際に滋賀で災害が起こった場合の災害ボランティアセンター設置への対応がされることとなっている。
今回の東日本大震災では、社会福祉協議会はブロック派遣で宮城へ職員を派遣したり、行政もそれぞれの立場での支援を行っている。連絡会の構成団体もそれぞれ独自に支援活動を行っているが、連絡会としてボランティアやNPOのサポートを積極的に行っていくような仕組みになっていない。
滋賀のNPOは、災害支援を体系的に行うノウハウを備えているところが少なく、また、今回の東日本大震災では、独自に被災地支援を行っているNPOもあるが、そうした情報が一元化されていない。
さらに、県内NPOの災害対応の情報も把握できていないため、実際に滋賀で災害が起こった場合、協働型の災害ボランティアセンターの設置がスムーズにいかないことが予想される。
こうした現状を踏まえ、NPOの東日本大震災での被災支援活動状況やNPOとしての災害支援メニューのデータベース化を図ることにより、NPO側の災害対応スキルを磨くとともに、連絡会とNPOとの連携構築を図る。
加えて、NPOとして被災地支援を行いたいが、単独では支援活動ができない団体も多く、そうしたNPOの思いを実際の支援活動につなげる。
●事業内容
5本柱で事業を実施する。
1)滋賀NPO災害ボランティアネットワークの構築
・NPOの災害ボランティアネットワーク構築のための検討会議(滋賀県社会福祉協議会、中間支援N
POなどで構成する会議体)を運営する。
・「滋賀県災害ボランティア活動連絡会」とNPOとの連携調整をする。
・他自治体におけるネットワーク事例の調査を行う。
2)NPOの災害支援データベースの作成
・県内NPOに対し、災害支援メニューづくりのための調査を行い、データベース化する。
・あわせて、東日本大震災への支援活動の調査も行う。
3)東日本大震災被災地支援活動
・ボランティアバスを被災地へ派遣する(NPOの特徴を活かし、災害支援メニューで挙がってきた中か
ら、検討会議で選定したプロジェクトを組んで行う)
4)報告会・成果フォーラムの開催(3月)
5.)NPO災害ネットワークの構築
・滋賀県外のNPOとのネットワークの構築を検討する。
4,業務の具体的な進め方と手順 (案)
1)滋賀NPO災害ボランティアネットワークの構築
・会議体であるネットワーク構築会議を行う。「滋賀NPO災害ボランティアネットワーク構築会議」を意思決
定機関として本事業を実施する。事務局はしがNPOセンターが担う。
・会議体の名簿作成をしつつ、さらに団体を拡大していく。情報共有の方法なども考える。
・事例調査を行う。他地域のNPO災害ネットワークの事例など。
2)NPOの災害支援データベースの作成
・調査を行うデータベース化する。被災支援プロジェクトへとつなげていく。
会議体で、データベース項目の検討なども行う。
3)東日本大震災被災地支援活動
・被災地支援プロジェクトの検討
会議体メンバーや、NPOからの発案により検討する。
バスに限らず、予算内で必要に応じて動く。
4)報告会・成果フォーラムの開催(3月)
・東日本大震災の支援活動報告会を1年目に行った。2年目(今年度)には最終的な成果をまとめるフォーラムを
開催する。
5)NPO災害ネットワークの構築
・滋賀県外のNPOとのネットワークの構築を検討する。
他地域の活動の調査
他地域の活動への参加
他地域の活動へのリンク など
災害支援に活かす“NPOの力”~いざという時の顔の見える関係づくり~
台風18号災害ボランティア情報共有会記録
災害支援市民ネットワークしが設立総会のご案内
3月20日シンポジウム、ありがとうございました
事務局長はこの前ラジオ(エフエム滋賀)に出演してきました
台風18号災害ボランティア情報共有会記録
災害支援市民ネットワークしが設立総会のご案内
3月20日シンポジウム、ありがとうございました
事務局長はこの前ラジオ(エフエム滋賀)に出演してきました
Posted by しがNPOセンター at 14:22
│しがNPO災害ボランティアネットワーク検討会議