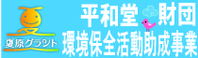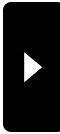2014年03月03日
情報を読み解く力
しがNPOセンター 代表理事
阿部圭宏
==========
以前のコラムで、「日本社会を見つめ直す視座」を持つことが必要で、そのための自分で情報を収集し分析するとともに、議論する場の構築が求められると書いた。ある事象について、賛成か反対かという単純な二分法に解消することが必ずしも正解とはならず、どのように結論づけるのかを悩みながら考えるという過程が求められる。そのために、書店や図書館へ出かけ、自ら関心領域の本を探し出して、とにかく読む、思考するということを繰り返すこと。と書くと、本離れが進んで、本など読む人はいないという話になってしまう。
昔なら、新聞、テレビ、雑誌などを組み合わせて情報収集すれば、だいたいのことが分かり、自分としての判断ができると思うことができた。しかし、今は、こうしたメディアが劣化し、本当に知りたい情報を知ることができないと言われている。コトの本質が問われなくなり、反論を許さず、多数派が形成されていくのに、メディアが加担しているという見方もできる。例えば、テレビでニュース、ワイドショー、ドキュメンタリーなどを見ていると、通常はすべて真実だと思ってしまい、そこにあまり疑問を挟まないことが多いのではないか。森達也は、著書の中で、「表現の本質は欠落にある」と言い切る。今のテレビは、テロップ、モザイク、ボイスオーバー(声優による吹き替え)、効果音、BGMなどが氾濫し、結局、事象が単純化されてしまい、結果として思考能力を奪ってしまっている。こうした傾向は、ネットの世界でもっとはっきりと現れる。「決められる政治」「あなたは賛成か反対か」「私が責任を持って決める」とか、政治家をはじめとする居丈高に叫ぶ人たちへのネットでの支持は高く、異を唱える者への誹謗は後を絶たない。根拠のない情報が一人歩きすこともよくある話だ。
では、メディアの劣化にどのように対抗するか。一言で言えば「リテラシー」を身に付けるということになる。リテラシーは使いこなす能力のことで、メディア・リテラシーは、さまざまな情報媒体を読み解いて、評価し、活用していく能力のことだと言える。原発事故では、明らかに市民がメディアに対する批判を行い、メディアに対する信頼性が一気に低下した。テレビや新聞では真実を得られないと考えた市民が、独自に専門家からの情報をネットで情報提供するなど、さまざまな実践が行われたと言われている。まさに、リテラシーが働いた数少ない事例と言えよう。
メディア・リテラシーをどのように身に付けるのかというと、自分で正しい情報を選びとり、手に入れるしかないというアイロニカルな結論になってしまう。確かに、本を何冊も読むのは時間がないという人もいるだろう。そうした場合、情報入手手段はいろいろあるので、多様な情報をそこからとってきて、批判的に評価をしてみるのも一つの方法かもしれない。例えば、ネット情報は溢れているので、いろんな意見を収集するにはてっとり早く、多様な情報の中から判断力を養うことができるようになるかもしれない。
とにかく、民主主義という仕組みをしっかりと機能させ、ポピュリズムに陥らせないようにするためにも、市民自身がメディア・リテラシーは必要だということの自覚を持つことが大切である。
阿部圭宏
==========
以前のコラムで、「日本社会を見つめ直す視座」を持つことが必要で、そのための自分で情報を収集し分析するとともに、議論する場の構築が求められると書いた。ある事象について、賛成か反対かという単純な二分法に解消することが必ずしも正解とはならず、どのように結論づけるのかを悩みながら考えるという過程が求められる。そのために、書店や図書館へ出かけ、自ら関心領域の本を探し出して、とにかく読む、思考するということを繰り返すこと。と書くと、本離れが進んで、本など読む人はいないという話になってしまう。
昔なら、新聞、テレビ、雑誌などを組み合わせて情報収集すれば、だいたいのことが分かり、自分としての判断ができると思うことができた。しかし、今は、こうしたメディアが劣化し、本当に知りたい情報を知ることができないと言われている。コトの本質が問われなくなり、反論を許さず、多数派が形成されていくのに、メディアが加担しているという見方もできる。例えば、テレビでニュース、ワイドショー、ドキュメンタリーなどを見ていると、通常はすべて真実だと思ってしまい、そこにあまり疑問を挟まないことが多いのではないか。森達也は、著書の中で、「表現の本質は欠落にある」と言い切る。今のテレビは、テロップ、モザイク、ボイスオーバー(声優による吹き替え)、効果音、BGMなどが氾濫し、結局、事象が単純化されてしまい、結果として思考能力を奪ってしまっている。こうした傾向は、ネットの世界でもっとはっきりと現れる。「決められる政治」「あなたは賛成か反対か」「私が責任を持って決める」とか、政治家をはじめとする居丈高に叫ぶ人たちへのネットでの支持は高く、異を唱える者への誹謗は後を絶たない。根拠のない情報が一人歩きすこともよくある話だ。
では、メディアの劣化にどのように対抗するか。一言で言えば「リテラシー」を身に付けるということになる。リテラシーは使いこなす能力のことで、メディア・リテラシーは、さまざまな情報媒体を読み解いて、評価し、活用していく能力のことだと言える。原発事故では、明らかに市民がメディアに対する批判を行い、メディアに対する信頼性が一気に低下した。テレビや新聞では真実を得られないと考えた市民が、独自に専門家からの情報をネットで情報提供するなど、さまざまな実践が行われたと言われている。まさに、リテラシーが働いた数少ない事例と言えよう。
メディア・リテラシーをどのように身に付けるのかというと、自分で正しい情報を選びとり、手に入れるしかないというアイロニカルな結論になってしまう。確かに、本を何冊も読むのは時間がないという人もいるだろう。そうした場合、情報入手手段はいろいろあるので、多様な情報をそこからとってきて、批判的に評価をしてみるのも一つの方法かもしれない。例えば、ネット情報は溢れているので、いろんな意見を収集するにはてっとり早く、多様な情報の中から判断力を養うことができるようになるかもしれない。
とにかく、民主主義という仕組みをしっかりと機能させ、ポピュリズムに陥らせないようにするためにも、市民自身がメディア・リテラシーは必要だということの自覚を持つことが大切である。
Posted by しがNPOセンター at 10:14
│シリーズ【阿部コラム】