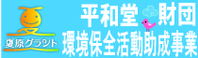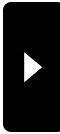2013年11月01日
災害情報の一元化
しがNPOセンター 代表理事
阿部圭宏
自然災害が頻発している。今年だけでも、火山噴火、竜巻、大雨洪水、台風などにより各地に多大な被害が出た。東日本大震災の経験から言われていたことであるが、もはや災害は対岸の火事ではないということを改めて認識させられた。滋賀はこれまで災害の少ない県と言われてきたが、台風18号では県内各地に大きな被害が出た。運用されたばかりの大雨特別警報が出され、それはテレビニュースですぐに確認できたが、出された警報に対して何をどうすればよいのかが分からないというのが一般的な市民の感想だろう。避難勧告や避難指示が県内あちこちで出されたが、伝達方法は自治体によってまちまちであったという。結果として、うまく対象地域の住民に避難情報が伝わっていなかったケースもあるようだ。
災害が起こったときに、どのように的確な情報を得るかが問われている。実際、テレビや自治体ホームページで確認していたが、入手できる情報は案外少なく、しかも断片的だというのが実感である。テレビで映し出されている映像では、場所を特定することが難しいこともあるし、ホームページで提供される行政情報は文字が多いためにリアリティを感じにくいなど、せっかく提供されている情報内容がうまく市民に伝わらないことも多い。また、後日県内を回り、マスコミ報道されていないところでも大きな被害が出ているのを身近に見て、大規模災害での全体像をつかむことの難しさを痛感した。
パソコンやスマホに慣れ親しんでいる人であれば、フェイスブック、ツイッター、動画サイトなどで、災害情報に簡単にアクセスできたはずだ。最近は、竜巻被害のときなど、テレビでも視聴者からの動画を流していることもよくあり、今やパソコンやスマホは、身近な情報ツールと言える。ウェザーニュースがやっているウェザーリポートは、市民からの情報提供で成り立っている。これまで一方的に情報を受け取る側だった市民が、情報提供側に回るという仕組みで、情報の双方向性がこれからのトレンドとなる勢いだ。これはあくまでアイデアであるが、こうした市民からの情報提供や情報発信を活かし、県内各地の道路、河川、被害状況などの情報を集約して、一つの地図上にまとめて表示できれば、スピード感を持って多くの情報を提供でき、大いに役に立つように思われる。

5月に立ち上げた「災害支援市民ネットワークしが」では、フェイスブックページを活用して、メンバーが収集した情報を掲載した。県内で立ち上がった災害ボランティアセンターの活動やボランティア募集の情報をあわせて掲載することで、ボランティア活動をしたいと思っている方への情報提供の一助になれたのではないかと考える。ただ、やはり問題として残るのは、こうした情報にアクセスできない情報弱者と呼ばれる人たちへの対応である。情報技術は便利であるが、災害が起こったときには、身近なところで助けてと言える人と人との関係づくりの再構築も必要である。
阿部圭宏
自然災害が頻発している。今年だけでも、火山噴火、竜巻、大雨洪水、台風などにより各地に多大な被害が出た。東日本大震災の経験から言われていたことであるが、もはや災害は対岸の火事ではないということを改めて認識させられた。滋賀はこれまで災害の少ない県と言われてきたが、台風18号では県内各地に大きな被害が出た。運用されたばかりの大雨特別警報が出され、それはテレビニュースですぐに確認できたが、出された警報に対して何をどうすればよいのかが分からないというのが一般的な市民の感想だろう。避難勧告や避難指示が県内あちこちで出されたが、伝達方法は自治体によってまちまちであったという。結果として、うまく対象地域の住民に避難情報が伝わっていなかったケースもあるようだ。
災害が起こったときに、どのように的確な情報を得るかが問われている。実際、テレビや自治体ホームページで確認していたが、入手できる情報は案外少なく、しかも断片的だというのが実感である。テレビで映し出されている映像では、場所を特定することが難しいこともあるし、ホームページで提供される行政情報は文字が多いためにリアリティを感じにくいなど、せっかく提供されている情報内容がうまく市民に伝わらないことも多い。また、後日県内を回り、マスコミ報道されていないところでも大きな被害が出ているのを身近に見て、大規模災害での全体像をつかむことの難しさを痛感した。
パソコンやスマホに慣れ親しんでいる人であれば、フェイスブック、ツイッター、動画サイトなどで、災害情報に簡単にアクセスできたはずだ。最近は、竜巻被害のときなど、テレビでも視聴者からの動画を流していることもよくあり、今やパソコンやスマホは、身近な情報ツールと言える。ウェザーニュースがやっているウェザーリポートは、市民からの情報提供で成り立っている。これまで一方的に情報を受け取る側だった市民が、情報提供側に回るという仕組みで、情報の双方向性がこれからのトレンドとなる勢いだ。これはあくまでアイデアであるが、こうした市民からの情報提供や情報発信を活かし、県内各地の道路、河川、被害状況などの情報を集約して、一つの地図上にまとめて表示できれば、スピード感を持って多くの情報を提供でき、大いに役に立つように思われる。

5月に立ち上げた「災害支援市民ネットワークしが」では、フェイスブックページを活用して、メンバーが収集した情報を掲載した。県内で立ち上がった災害ボランティアセンターの活動やボランティア募集の情報をあわせて掲載することで、ボランティア活動をしたいと思っている方への情報提供の一助になれたのではないかと考える。ただ、やはり問題として残るのは、こうした情報にアクセスできない情報弱者と呼ばれる人たちへの対応である。情報技術は便利であるが、災害が起こったときには、身近なところで助けてと言える人と人との関係づくりの再構築も必要である。
Posted by しがNPOセンター at 17:37
│シリーズ【阿部コラム】
この記事へのコメント
すきまかぜ編集部
災害OUT・SIDEの正村です
阪神淡路大震災から情報ボランティアをしてますが、災害情報の難しさは情報の賞味期限をどう図るか?
情報は玉手箱みたいに考えられますが・・
時間がたつとてんこ盛り状態になって、必要な情報を得ようにも探すことが難しい状況になることがあります。
この情報が今直ぐ必要なのか?
発信から3日間必要なのか?
続けて出さないといけない情報なのか?
1997年の日本海重油流出事故災害で初めてボランティアが自身の情報発信ツールとしてホームページを立ち上げました
当時の情報ツールは報道機関しかなかったですが・・
NHKが明日のボランティアは予定通り開催します・・って出して
翌日の天気で風雨があり中止にしたら・・
テレビでは開催するって遣ってたぞ・・って事でボランティアと本部間で小競り合いがあったしね・・
テレビの情報で言えば毎回柄杓で油を掬う映像が流れ続けた事で何万本もの柄杓が送られてきて・・被災地自治体では柄杓を保存するのに数千万円の倉庫代を出し続けたって笑い話もありますね・・
災害情報の重要性は20年近く係ってきているので必要だと思いますが・・賞味期限やその情報の信ぴょう性などを管理されるシステム管理者を置く事と・・疑わしい情報を削除するかどうかの判断・・本文で述べられている情報弱者への伝達方法・・情報を読み解く(リテラシー)能力の啓発が必要だと思いますね・・
災害OUT・SIDE
Email:saigaioutside@yahoo.co.jp
代表 正村圭史郎
災害OUT・SIDEの正村です
阪神淡路大震災から情報ボランティアをしてますが、災害情報の難しさは情報の賞味期限をどう図るか?
情報は玉手箱みたいに考えられますが・・
時間がたつとてんこ盛り状態になって、必要な情報を得ようにも探すことが難しい状況になることがあります。
この情報が今直ぐ必要なのか?
発信から3日間必要なのか?
続けて出さないといけない情報なのか?
1997年の日本海重油流出事故災害で初めてボランティアが自身の情報発信ツールとしてホームページを立ち上げました
当時の情報ツールは報道機関しかなかったですが・・
NHKが明日のボランティアは予定通り開催します・・って出して
翌日の天気で風雨があり中止にしたら・・
テレビでは開催するって遣ってたぞ・・って事でボランティアと本部間で小競り合いがあったしね・・
テレビの情報で言えば毎回柄杓で油を掬う映像が流れ続けた事で何万本もの柄杓が送られてきて・・被災地自治体では柄杓を保存するのに数千万円の倉庫代を出し続けたって笑い話もありますね・・
災害情報の重要性は20年近く係ってきているので必要だと思いますが・・賞味期限やその情報の信ぴょう性などを管理されるシステム管理者を置く事と・・疑わしい情報を削除するかどうかの判断・・本文で述べられている情報弱者への伝達方法・・情報を読み解く(リテラシー)能力の啓発が必要だと思いますね・・
災害OUT・SIDE
Email:saigaioutside@yahoo.co.jp
代表 正村圭史郎
Posted by すきまかぜ編集部 at 2013年11月02日 00:06
at 2013年11月02日 00:06
 at 2013年11月02日 00:06
at 2013年11月02日 00:06正村さま
阿部です。ご意見ありがとうございます。確かにリテラシーは重要ですね。
阿部です。ご意見ありがとうございます。確かにリテラシーは重要ですね。
Posted by 阿部圭宏 at 2013年11月05日 11:52