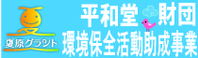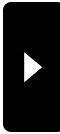2016年01月04日
三権分立とは何かを考える
新年あけましておめでとうございます。本コラムをご愛読いただきましてありがとうございます。今年も議論ができる話題を取り上げていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
しがNPOセンター 代表理事
阿部圭宏
---------------
年末に注目される判決があった。一つは、離婚した女性は6カ月間再婚できないとする民法の規定が、100日を超える部分は憲法違反だとした最高裁判決であり、もう一つは、夫婦同姓の制度は憲法に違反しないという最高裁の判断である。さらに、福井地裁では、 関西電力高浜原発3・4号機の再稼働をめぐり、安全性に欠けるとは言えないと、再稼働を即時差し止めた4月の仮処分決定を取り消した。
こうした裁判所の判断を見聞きして、皆さんはどのように感じただろうか。民法の見直しは戦後改革の中でも放ったらかしにされてきたところで、最高裁を頂点とする司法が時代についていけていない状況を改めて感じた。大井原発の判断では、裁判官を変えてまで国策に妥協しようとする司法官僚の世界を見た気がする。
司法の世界には統治行為論という考えがあるとされる。高度な政治性を有する国家の行為については、裁判所による法律判断が可能であっても司法審査の対象から除外すべきとする考え方で、今回の判例も直接的とは言わないまでも、こうした考え方を土台にしているようにも思われる。市民にとって最後の救済の場であるべき司法が自制を利かしすぎれば、本当にこれで人権が守られるのかという疑念がわく。
年末にはもう一つ行政の世界でも大きな判断があった。総務省所管の第三者機関・国地方係争処理委員会が米軍普天間飛行場の県内移設に関する政府の対応を是正させるよう求めた沖縄県の翁長雄志知事の申し出を却下することを多数決で決めた。国と地方との係争を処理するという鳴り物入りでできた委員会も、結局、地方を向かずに国の論理で動くのだということを改めて思い知らされた。それよりも重大なのは、そもそも県の処分に対する不服申し立てを国の機関が国の機関に対して行うことの正当性がどこにあるのか。法律の解釈権は国の機関にしかないのだという行政の傲慢の表れだとも思われる。
司法や行政と立法という政治に関わる権力が分立し、お互いを牽制し合うことで権力の乱用を防ぐのだという「三権分立」は、学校で習う誰もが知っているものだ。日本のような議院内閣制における三権分立では、多数派が内閣を組織するため、立法権と行政権との分立は緩やかであるが、ここではそれが問題なのではない。行政権力が強いことに加え、それに司法が引っ張られている状況に、ある種行政への権力集中が起こっていることが問題だと言っているのだ。
では、こうした司法や行政をどうすべきか。司法改革が裁判員制度に矮小化されて、その本体が旧態依然としていることから、裁判のあり方も市民がもっとウォッチしていく必要があるだろう。行政の権力集中についはどう考えるか。権力分散は必要だが、これはなかなか難しい問題だ。とりあえずは、霞が関の視点だけが闊歩するような社会システムの変革を考えていく必要がある。そのため、地方分権を進め、あわせて権力を市民一人ひとりに分散させていくことからしか始まらないような気がする。
今回のテーマを考える上での参考文献
新藤宗幸著『司法官僚-裁判所の権力者たち』(岩波新書、2009年)
國分功一郎『来るべき民主主義―小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題』
(幻冬舎新書、2013年)
待鳥聡史『代議制民主主義-「民意」と「政治家」を問い直す』(中公新書、2015年)
しがNPOセンター 代表理事
阿部圭宏
---------------
年末に注目される判決があった。一つは、離婚した女性は6カ月間再婚できないとする民法の規定が、100日を超える部分は憲法違反だとした最高裁判決であり、もう一つは、夫婦同姓の制度は憲法に違反しないという最高裁の判断である。さらに、福井地裁では、 関西電力高浜原発3・4号機の再稼働をめぐり、安全性に欠けるとは言えないと、再稼働を即時差し止めた4月の仮処分決定を取り消した。
こうした裁判所の判断を見聞きして、皆さんはどのように感じただろうか。民法の見直しは戦後改革の中でも放ったらかしにされてきたところで、最高裁を頂点とする司法が時代についていけていない状況を改めて感じた。大井原発の判断では、裁判官を変えてまで国策に妥協しようとする司法官僚の世界を見た気がする。
司法の世界には統治行為論という考えがあるとされる。高度な政治性を有する国家の行為については、裁判所による法律判断が可能であっても司法審査の対象から除外すべきとする考え方で、今回の判例も直接的とは言わないまでも、こうした考え方を土台にしているようにも思われる。市民にとって最後の救済の場であるべき司法が自制を利かしすぎれば、本当にこれで人権が守られるのかという疑念がわく。
年末にはもう一つ行政の世界でも大きな判断があった。総務省所管の第三者機関・国地方係争処理委員会が米軍普天間飛行場の県内移設に関する政府の対応を是正させるよう求めた沖縄県の翁長雄志知事の申し出を却下することを多数決で決めた。国と地方との係争を処理するという鳴り物入りでできた委員会も、結局、地方を向かずに国の論理で動くのだということを改めて思い知らされた。それよりも重大なのは、そもそも県の処分に対する不服申し立てを国の機関が国の機関に対して行うことの正当性がどこにあるのか。法律の解釈権は国の機関にしかないのだという行政の傲慢の表れだとも思われる。
司法や行政と立法という政治に関わる権力が分立し、お互いを牽制し合うことで権力の乱用を防ぐのだという「三権分立」は、学校で習う誰もが知っているものだ。日本のような議院内閣制における三権分立では、多数派が内閣を組織するため、立法権と行政権との分立は緩やかであるが、ここではそれが問題なのではない。行政権力が強いことに加え、それに司法が引っ張られている状況に、ある種行政への権力集中が起こっていることが問題だと言っているのだ。
では、こうした司法や行政をどうすべきか。司法改革が裁判員制度に矮小化されて、その本体が旧態依然としていることから、裁判のあり方も市民がもっとウォッチしていく必要があるだろう。行政の権力集中についはどう考えるか。権力分散は必要だが、これはなかなか難しい問題だ。とりあえずは、霞が関の視点だけが闊歩するような社会システムの変革を考えていく必要がある。そのため、地方分権を進め、あわせて権力を市民一人ひとりに分散させていくことからしか始まらないような気がする。
今回のテーマを考える上での参考文献
新藤宗幸著『司法官僚-裁判所の権力者たち』(岩波新書、2009年)
國分功一郎『来るべき民主主義―小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題』
(幻冬舎新書、2013年)
待鳥聡史『代議制民主主義-「民意」と「政治家」を問い直す』(中公新書、2015年)
Posted by しがNPOセンター at 11:02
│シリーズ【阿部コラム】