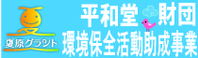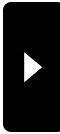2019年04月01日
滋賀県行政の難しさ
しがNPOセンター
代表理事 阿部 圭宏
2000年の地方分権一括法の施行以来、都道府県は、市町村と対等・協力の関係にある地方自治体として自らを位置づけ、拡大した地域における事務等を自主的・自立的に処理し、地域住民の福祉向上を図っていくことが必要とされるようになった。
話を滋賀に絞って考えてみよう。分権の流れは、一方で合併へと繋がり、市町村数は、これまで7市42町1村であったものが13市6町と、ほぼ3分の1に減った。これだけ市が増えたことで、県と市町の関係も対等・協力という視点からは、この20年間で力関係が市町へ移り、県の存在が見えなくってきているのは確かな事実だ。
基礎自治体である市町は、地域における事務等を処理するのに対して、県は、市町を包括する広域自治体として、広域事務、連絡調整事務及び補完事務を処理するものとされている。そういう意味では、県が最新情報を持ちつつ、市町と協力しながら物事を進めていくというのが一つの形になるだろう。
実際、「琵琶湖における市町境界」を設定することで、新たに算入される地方交付税を琵琶湖の総合保全対策に資する施策の展開があった。これは、従来未確定であった境界を確定することで、市町の交付税算定額をあげるとともに、県が調整することで、琵琶湖の保全も図ろうとするものであった。県が主体的に市町間の利害調整を行うのは、広域事務、連絡調整事務の根幹をなすものと言える。
しかし、市町からすれば、こうした事例のように、県がうまく調整を図ってくれることの方が少なくて、不満が多いのではなかろうか。そこには、住民と向き合う立場の違いがある。例えば、子育て支援の立場からの保育士の確保や処遇改善、地域交通の確保などは、市町行政にとって喫緊の重要課題である。県にとっては、金のないこともあって財政的な負担を県単独でするという考えになりにくい。となると、自ずと県と市町の考えにズレが生じる。
昔のように、市町が県を頼ってくれる縦関係であればよかったと思っている県職員もいるかもしれないが、そういう時代は終わった。常に新しい情報を持ちながら、市町の邪魔をしないで、国と渡り合う。果たしてこんなことを県に臨んで叶うのか。
代表理事 阿部 圭宏
2000年の地方分権一括法の施行以来、都道府県は、市町村と対等・協力の関係にある地方自治体として自らを位置づけ、拡大した地域における事務等を自主的・自立的に処理し、地域住民の福祉向上を図っていくことが必要とされるようになった。
話を滋賀に絞って考えてみよう。分権の流れは、一方で合併へと繋がり、市町村数は、これまで7市42町1村であったものが13市6町と、ほぼ3分の1に減った。これだけ市が増えたことで、県と市町の関係も対等・協力という視点からは、この20年間で力関係が市町へ移り、県の存在が見えなくってきているのは確かな事実だ。
基礎自治体である市町は、地域における事務等を処理するのに対して、県は、市町を包括する広域自治体として、広域事務、連絡調整事務及び補完事務を処理するものとされている。そういう意味では、県が最新情報を持ちつつ、市町と協力しながら物事を進めていくというのが一つの形になるだろう。
実際、「琵琶湖における市町境界」を設定することで、新たに算入される地方交付税を琵琶湖の総合保全対策に資する施策の展開があった。これは、従来未確定であった境界を確定することで、市町の交付税算定額をあげるとともに、県が調整することで、琵琶湖の保全も図ろうとするものであった。県が主体的に市町間の利害調整を行うのは、広域事務、連絡調整事務の根幹をなすものと言える。
しかし、市町からすれば、こうした事例のように、県がうまく調整を図ってくれることの方が少なくて、不満が多いのではなかろうか。そこには、住民と向き合う立場の違いがある。例えば、子育て支援の立場からの保育士の確保や処遇改善、地域交通の確保などは、市町行政にとって喫緊の重要課題である。県にとっては、金のないこともあって財政的な負担を県単独でするという考えになりにくい。となると、自ずと県と市町の考えにズレが生じる。
昔のように、市町が県を頼ってくれる縦関係であればよかったと思っている県職員もいるかもしれないが、そういう時代は終わった。常に新しい情報を持ちながら、市町の邪魔をしないで、国と渡り合う。果たしてこんなことを県に臨んで叶うのか。
Posted by しがNPOセンター at 10:00
│シリーズ【阿部コラム】